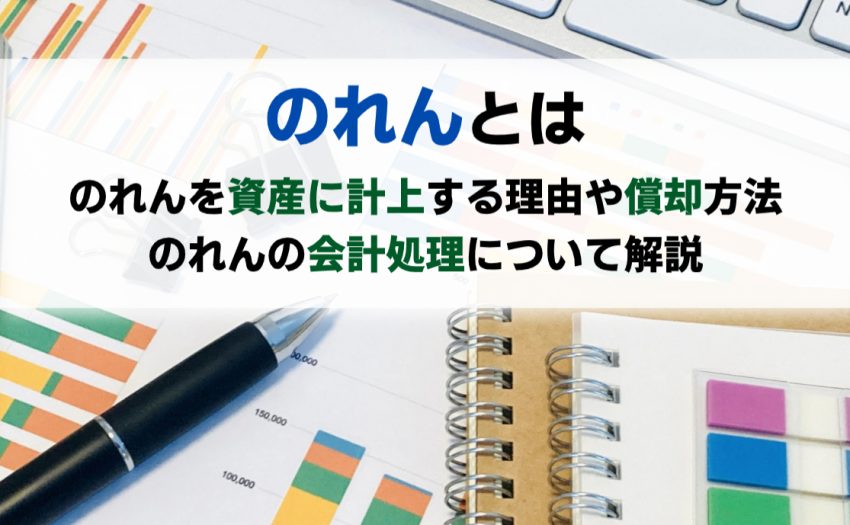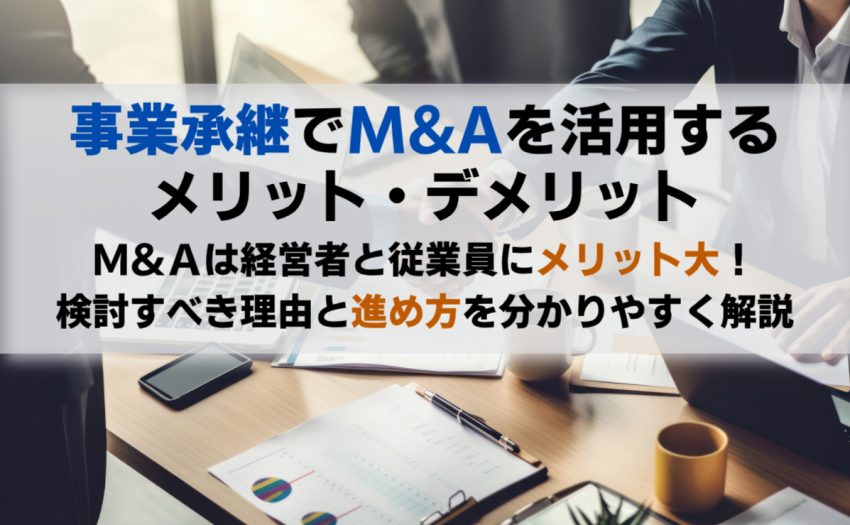経営セーフティ共済の5つのメリットと2つのデメリット
公開日:2019年12月12日
最終更新日:2024年02月14日
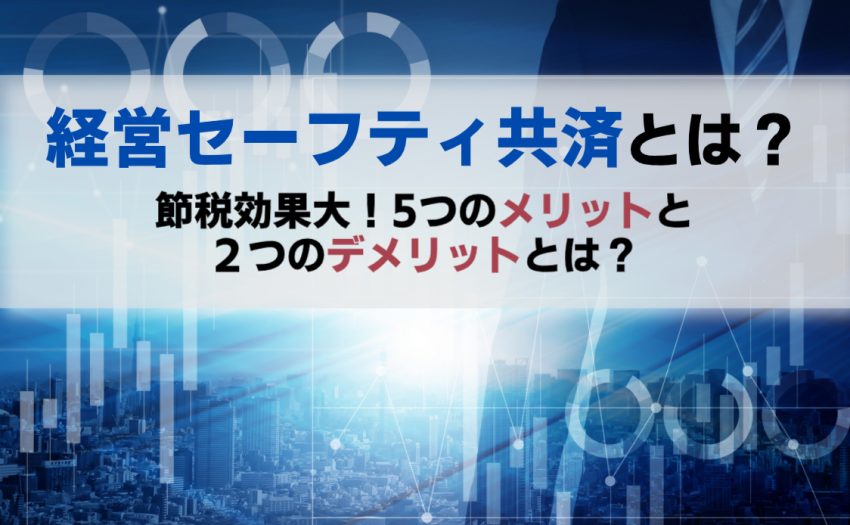
目次
この記事のポイント
- 経営セーフティ共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度。
- 無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入ができる。
- 掛金の税制優遇措置が受けられるので、節税効果がある。
経営セーフティ共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、取引先が倒産してしまった際に巻き込まれて連鎖倒産したり、経営難になったりすることを防ぐことを目的とした制度です。
共済に加入することで貸付制度が受けられるようになるほか、事業所得なら年間最大480万円(20万円×12カ月)が必要経費(法人の場合は損金)になるなど、多くのメリットのある制度です。
経営セーフティ共済の豆知識
中小企業の倒産原因で多いのが「連鎖倒産」です。個人事業主や中小企業では、一般的に連鎖倒産に耐えるだけの十分な資金力を持つのが厳しいといえます。経営セーフティ共済は、このような状況を防ぐことを目的とした国の支援制度です。
経営セーフティ共済は、本来は連鎖倒産を防ぐことが目的の制度ですが、支払う掛金は全額事業の必要経費に計上することができるので、定期預金の積立額が経費になるのと同じ効果がある節税効果大の制度です。また、取引先が倒産して売掛金が回収できない場合には無利子で貸付を受けることができますし、掛金の納付月数が40カ月以上になれば、任意解約することができるので全額返金されます。
個人事業主や中小企業の節税対策として活用できる共済制度は、この経営セーフティ共済以外にも中小企業退職金共済制度や小規模企業共済などがあります。詳しくは税理士に相談して、アドバイスを受けることをおすすめします。
経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済とは、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産したり経営難に陥ったりすることを防ぐことを目的とした共済制度です。
継続して1年以上事業を継続している個人事業主、または一定の条件に該当する中小企業者が加入できます。
この制度は、中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。
参照:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済」
(1)経営セーフティ共済の支援内容
経営セーフティ共済は、加入後6カ月が経過して取引先企業が倒産した場合(一定要件を満たす私的整理も含みます)、売掛金や受取手形の回収が困難になった額と、積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない方の額(貸付限度額8,000万円)の貸付を受けることができます。
その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借入ができるので連鎖倒産を防ぐことに効果があるというわけです。
なお、借入に際しては、担保・保証料の必要はありません。
| 借入額 | 返済期間(6か月の据置期間含む) |
| 5,000万円未満 | 5年 |
| 5,000万円以上6,500万円未満 | 6年 |
| 6,500万円以上8,000万円以下 | 7年 |
(2)経営セーフティ共済の掛金と加入条件
経営セーフティ共済の掛金は、月額5,000円から20万円の範囲内で、設定することができます(5,000円きざみ)。また、加入後増額することもできます。
加入条件は、1年以上継続して事業を行っている中小企業者で、かつ次の表の「資本金額等」または「従業員数」のいずれかに該当する会社であれば、加入することができます
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
経営セーフティ共済の5つのメリット
「自社の取引先は倒産する可能性が低いから、自分には関係ない制度だ」と思われる方もいるかもしれません。しかし、経営セーフティ共済は、取引先が倒産する可能性がなくても、急に資金が必要になった時には解約手当金の範囲内で借入をすることができます。その他にも、これからご紹介するように多くのメリットのある制度です。
(1)節税効果がある
まず、この制度の一番のメリットが、掛金の税制優遇で高い節税効果があるという点です。経営セーフティ共済に加入すれば、確定申告の際にはその掛金を損金(個人事業主は必要経費)に算入することができるので、たとえば掛金を月額20万円にすれば最大で年間240万円(20万円×12カ月)を損金に算入することができます。
つまり、その分所得を減らし節税することができるのです。
(2)取引先が倒産後すぐに借入できる
取引先が倒産して、売掛金などの回収が困難になった時には、その事業者との取引が確認され次第、すぐに借入をすることができます。
共済金の借入れが受けられる取引先の倒産は以下のとおりです。
なお、取引先が夜逃げしてしまったケースについては、共済金の借入はできません。
|
・法的整理 ・取引停止処分 ・でんさいネットの取引停止処分 ・私的整理 ・災害による不渡り ・災害によるでんさいの支払不能 ・特定非常災害による支払不能 |
(3)掛金は加入後変更可能
掛金は5,000円から20万円の間で自由に選ぶことができ、加入後増額・減額もできます。
増額・減額したい時には、それぞれ以下の手続きを行います。
・増額をしたい時
増額を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が書類を受理すれば、その希望月から増額後の掛金月額で引き落としされます。
・減額をしたい時
減額を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が書類を受理すれば、その希望月から減額後の掛金月額で引き落としされます。
なお、掛金は800万円まで積立が可能です。掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合には、事前に納付掛止届出書を提出すれば、「掛金の払い止め」をすることができます。
(4)40カ月以上で掛金が100%戻る
40カ月以上の納付期間があれば、掛金の100%が戻ってきます。
ただし、解約手当金を受け取った時には課税されるので注意して下さい。
経営セーフティ共済は、あくまで緊急時に借入ができるという保険を掛けながら、掛金を損金にすることができる制度です。
つまり、毎期の納税額は少なくなりますが、解約手当金の入金時には一気に課税されるので、税負担という意味ではトータル的には変わりません。
しかし裏を返せば、保険料ゼロで取引先の倒産時に借入ができるという保証がされているということでもあるので、やはり非常にお得な制度であるということは間違いありません。
(5)一時貸付金が利用できる
一時貸付金とはは、取引先事業者が倒産していなくても、事業資金を必要とする場合には一時貸付金を利用できます。これは、解約時に支払われる解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。
公庫や保証協会系からの融資が実行されるのが遅くて待てないというような事情がある場合には、ぜひ活用したい制度です。
共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
| 掛金納付月数 | 一時貸付金の借入限度額 |
| 1か月~11か月 | 0円 |
| 12か月~23か月 | 掛金総額 × 75% × 95% |
| 24か月~29か月 | 掛金総額 × 80% × 95% |
| 30か月~35か月 | 掛金総額 × 85% × 95% |
| 36か月~39か月 | 掛金総額 × 90% × 95% |
| 40か月以上 | 掛金総額 × 95% × 95% |
| 掛金総額が800万円の場合 | 800万円 × 100% × 95%(760万円) |
経営セーフティ共済の2つのデメリット
多くのメリットのある経営セーフティ共済ですが、以下の2つのデメリットがあります。
(1)起業1年目の方には使えない
まず、加入資格が継続して1年以上事業を行っている個人事業主または中小企業者であるという点です。
つまり、起業して1年目は少しでも節税したいというケースが多いものですが、1年目に加入することはできないという点は、デメリットということができるでしょう。
(2)12カ月未満は掛金全額の戻りはない
共済契約を解約した時には、掛金を12カ月以上納めていれば、掛金総額の8割以上が戻り、40カ月以上納めていれば掛金全額が戻ります(ただし、解約時に税金はかかります)。つまり、12カ月未満は、掛け捨てになってしまうので、注意が必要です。
まとめ
経営セーフティ共済の掛金は、支払保険料として経費にして積立金として資産計上することができます。ただし、法人税申告書を作成する時には、「別表10(6)」という書類を添付する必要があります。
顧問税理士に決算申告を依頼するなら、その税理士に、経営セーフティ共済の掛金を支払ったことを伝えておけば申告書類の提出漏れはありませんが、そうでない場合には、どのような書類が必要でどのように記載をするべきかについて、事前に相談することをおすすめします。
税理士をお探しの方
freee税理士検索では数多くの事務所の中から、確定申告や節税対策について相談できる税理士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
\ 節税対策について相談できる税理士を検索 /
この記事の監修・関連記事

監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
クラウド会計ソフトの「クラウド会計ソフト freee会計」が、税務や経理などで使えるお役立ち情報をご提供します。
「クラウド会計ソフト freee会計」は、毎日の経理作業を最小限で終わらせることができるクラウド型会計ソフトです。疑問点や不明点は、freee税理士検索で税理士を検索し、相談することができます。