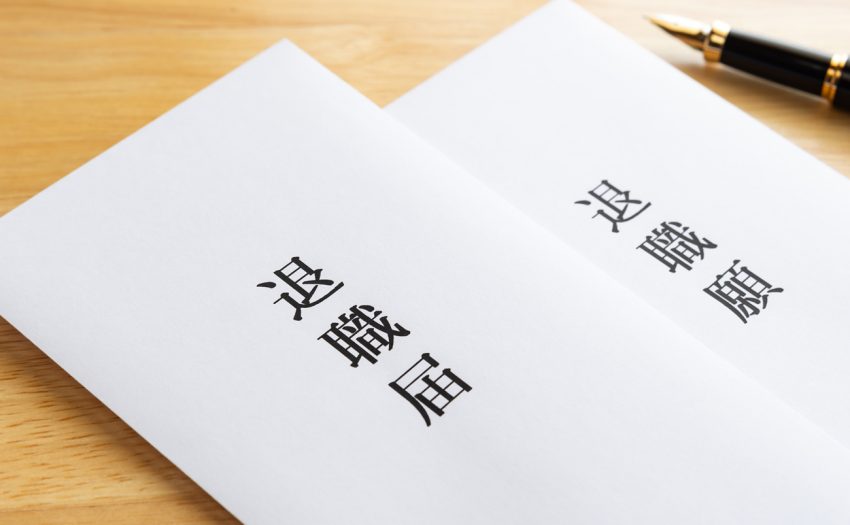従業員入社時の労災保険・雇用保険・社会保険の手続き
公開日:2019年12月02日
最終更新日:2022年07月14日

目次
この記事のポイント
- 従業員が入社したら、社会保険や雇用保険などの加入手続きが必要。
- 必要な手続きは、家族構成や雇用形態によって変わる。
- 従業員が入社したら、まず加入基準を満たしているか確認する。
従業員の入社が正式に決定した場合には、さまざまな入社手続きが必要です。
採用が正式に決定したら入社日や出社時刻などを通知しますが、同時に必要書類の提出を求め、「基礎年金番号」や「雇用保険の被保険者番号」について確認する必要あります。
また、新卒の場合には、卒業証書や成績証明書などの提出を求めることもあります。
従業員を採用した時の手続き
従業員の採用が正式に決定した場合には、各種保険の手続きをはじめ、いろいろな手続きが必要となります。
まずは労働条件を明示した労働契約書を締結する必要がありますし、マイナンバー、年金手帳、雇用保険被保険者証などが必要となります。
提出する書類に個人情報に関する事項が入る場合には、あらかじめその書類の利用目的を伝えなければなりません。
(1)労働契約書の締結
労働契約書(雇用契約書)とは、雇用主(会社)と従業員の両者間で、労働条件を明らかにするために交わす契約書をいいます。
会社は、採用者に対して「賃金を支払う義務」を負います。また、採用者は「使用されて労働する義務」を負います。これを労働契約といい、基本的には合意をしたうえで押印し、会社と従業員がそれぞれ1通ずつ保管します。
労働契約書では、労働契約の期間や就業の場所、従事する業務の内容、休憩、休日等を必ず明示しなければなりません。
また、入社前には、健康診断を行うことが義務づけられていますが、その代わりとして採用前3カ月前に健康診断を受けていれば、その診断書を提出してもらうことが認められています。
(2)健康保険の加入手続き
健康保険とは、日常生活でケガや病気となった時に、主に治療を受けるために使う保険です。健康保険の対象は、適用除外者以外の会社で雇用されている従業員です。
パートやアルバイトも労働時間と労働日数が、正社員の4分の3以上だと加入対象となります。
健康保険証は、事務センターまたは年金事務所に資格取得の届出をすると、協会けんぽから会社に交付されます。
健康保険の手続きは、入社手続きのなかでも最も急ぎたい手続きです。手続きが遅れて健康保険被保険者証の交付が遅れると、健康保険適用で診療できなくなる期間が長くなってしまうからです。
もし、健康保険被保険者証が交付されない間に従業員が病院に行く場合には「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」という書類を準備し、年金事務所等に提出すれば、健康保険被保険者証の代わりに病院に提出すると、健康保険適用で診療を受けることができます。
被保険者以外の人が手続きする場合には、委任状が必要となります。
(3)厚生年金保険の加入手続き
健康保険と厚生年金保険は、同時に加入手続きを行います。
協会けんぽに加入している事業所は、健康保険・厚生年金保険ともに年金事務所で加入手続きを行います。
厚生年金保険は70歳未満までしか加入できないので、70歳以上の従業員が入社したときは、健康保険のみ手続きを行います。
被扶養者がいる場合には、年金事務所で健康保険の扶養手続きと国民年金第3号被保険者の加入手続きも行います。
被扶養者の収入が確認できる書類が必要です。
健康保険組合に加入している事業所は、厚生年金保険は年金事務所で、健康保険は健康保険組合で加入手続きを行います。
年金事務所に提出する被保険者資格取得届には、マイナンバーや基礎年金番号の記載が必要です。被扶養者の加入手続きについては、健康保険は健康保険組合で、国民年金第3号被保険者加入手続きは年金事務所で行います。
健康保険と厚生年金保険の加入手続きには健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届という書類が必要です。資格取得届は、日本年金機構などのホームページからダウンロードできる他、年金事務所でもらうこともできます。
窓口で提出したり郵送したりすることもできますし、e-Gov電子申請などインターネットで提出することもできます。
(4)雇用保険の加入手続き
雇用保険の加入手続きは、ハローワークで行います。
従業員を新規に雇い入れた場合には、個々の従業員に対して雇用保険の資格取得手続きが必要です。この手続きは、従業員が入社した日の翌月10日までに行わなければなりません。
法律で適用除外とされる従業員(65歳以上の人や季節的な事業に4カ月以内の期間を定めて雇用される者など)を除いたすべての従業員が加入対象者となります。パート従業員も適用要件を満たす場合には、加入対象者となります。
雇用保険被保険者資格取得届には、雇用保険の被保険者番号とマイナンバーの記載欄があります。
前職などですでに雇用保険に加入したことがある人は、付与された被保険者番号があるのでその番号を記載します。
雇用保険被保険者証や離職票に記載されているので、あらかじめ従業員に確認しておきましょう。もしこれらの書類を紛失したなどの理由で被保険者番号がわからない場合は、資格取得届の備考欄に【前職の会社名や勤務期間】を記入すれば、ハローワークで被保険者番号を照会してくれます。
(5)住民税の特別徴収手続き
住民税は、自分で現住所の市区町村へ納付する「普通徴収」と、事業主が従業員を雇用している場合に、事業主が従業員から住民税を集めて代わりに市区町村へ納付する「特別徴収」があります。
中途入社など過去に所得がある入社者の場合には、「特別徴収にかかる給与所得者異動届」を提出してもらい、会社名、住所、特別徴収を開始する月等を記入して、各市区町村に提出します。
新卒入社など過去に所得がない入社者の場合には、住民税の特別徴収は2年目から発生します。
そのため、入社時の手続きは不要です。
(6)労災保険は従業員ごとの手続きは不要
従業員が1人でもいる会社は、労災保険に加入しなければなりません。
これは、アルバイトやパートを雇用した場合も同じです。
はじめて従業員を雇用した日が労災保険の加入日となりますので、この日から10日以内に労働基準監督署で加入手続きを行う必要があります。
労災保険は、正社員にかぎらず、アルバイトやパートを雇用した場合も、に加入しなければなりません。
従業員が1人でいる会社は加入が義務づけていて、1日限りのアルバイトを含め、会社に雇われる従業員を採用したら、速やかに加入手続きを行います。
労災保険は、従業員を雇用するたびに加入手続きをする保険ではなく、会社が事業所自体として加入し、その事業所で働いている従業員がすべて保険の対象となるしくみの制度です。
したがって労災保険は、はじめて従業員を雇用した日が労働保険の加入日となり、この日から10日以内に労働基準監督署で加入手続きをする必要がありますが、従業員が入社したり退社したりするたびに、その都度手続きが発生するというわけではなく、2人目以降の採用時には、労災保険の手続きは不要です。
freee人事労務の活用
社会保険・雇用保険の加入手続を行うためには、基礎年金番号や雇用保険の被保険者番号の確認が必要です。
これらの番号は口頭や書類で確認しなくても、従業員に「freee人事労務」で直接入力してもらうこともできます。
「freee人事労務」のベーシック以上のプランでは、以下の書類を作成することができます。
|
書類 |
対象 |
提出先 |
提出期限 |
|---|---|---|---|
|
社会保険加入の従業員 |
(健康保険組合に加入している場合)健康保険組合 年金事務所 |
入社日から5日以内 |
|
|
扶養親族がいる従業員 |
|||
|
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上引き続き雇用すると見込まれる従業員 |
ハローワーク |
入社日の翌月10日まで |
|
|
住民税の普通徴収から特別徴収への変更依頼届 |
住民税の納付が完了していない従業員のうち、4月1日に自社に在籍している予定であるか、特別徴収への切り替えを希望している従業員 |
従業員が居住する市区町村 |
普通徴収の納期限まで ※詳細は各市区町村へ確認 |
|
健康保険被保険者資格証明書交付申請書 |
全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者又は被扶養者となる人が早急に医療機関で受診する予定がある場合 |
年金事務所の窓口 | 任意 |
健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者にかかる届書は、入社時点に扶養親族がいる場合に限られます。入社後、扶養親族に変動があった場合には対応していません。
まとめ
以上、従業員が入社した時の社会保険手続き・雇用保険手続きについてご紹介いたしました。従業員が入社した時や退社した時には、必要な手続きが多いので、出来る限り早めに行うようにしましょう。
入社時の手続きについて相談する
freee税理士検索では数多くの事務所の中から、従業員の入退社手続きについて相談できる社会保険労務士を検索することができます。ぜひご活用ください。
この記事の監修・関連記事

監修:「クラウドfreee人事労務」
クラウドソフトの「クラウドfreee人事労務」が、人事労務で使えるお役立ち情報をご提供します。
「freee人事労務」は、複雑な労務事務を一つにまとめて、ミス・作業時間を削減します。法律や給与計算が分からないといったケースでも、ご安心ください。「使い方がわからない」「正しいやり方がわからない」をなくすための充実の導入サポート体制で、しっかりとご支援します。
また、人事労務に関する疑問点や不明点は、freee税理士検索で社会保険労務士や税理士を検索し、相談することができます。