決算前にできる節税対策を税理士が回答
公開日:2019年11月08日
最終更新日:2024年03月22日
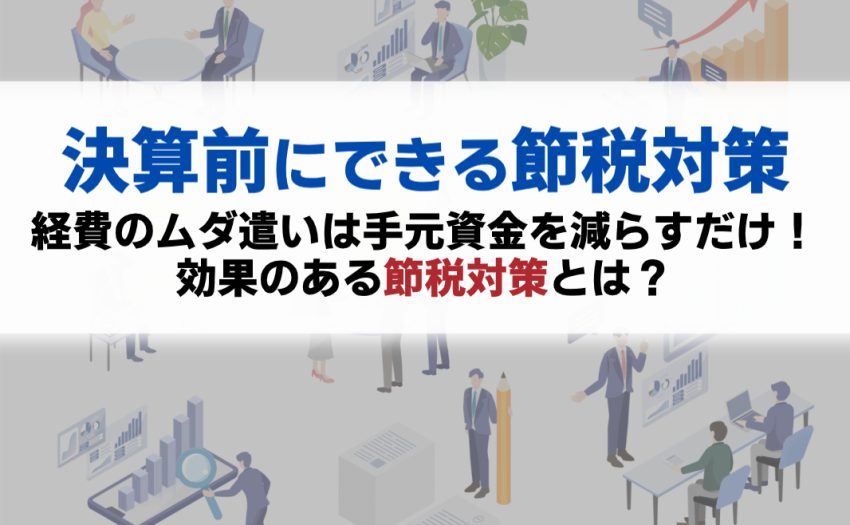
目次
この記事のポイント
- 節税対策は、中長期計画を立てて実行する方が、効果的である。
- 決算前でもできる節税対策もあるが、実行前には十分な検討が必要。
- 資金繰りが厳しい時には、仮決算や法人税の申告期限の延長を検討するのも有効。
決算前になると、「納税額を減らすために経費を使おう」と必要もない飲み会を開いたり、不要なパソコンを購入したりするケースがあります。
確かにこれらの費用がまとまった金額になれば、納税額を減らす効果はあります。しかし、このような方法で税金を減っても、無駄な経費を使えば結局のところ手元資金を減らすだけですから意味がありません。
そこで、この記事では税理士がおすすめできる「決算前でもできる節税対策」についてご紹介します。無駄な経費を使う前に、まずはこれらの方法を検討するようにしましょう。
節税対策の豆知識
節税対策とは、合法的な方法で支払う税金を減少または繰延して、会社内に残る資金を留保するための手法です。
適切な節税対策を行なえば、その資金で企業活動に投資することができますし、役員や従業員の生活を豊かにすることができます。
節税対策は、大企業より中小企業の方が有利です。
なぜなら、資本金等の小さい企業の方が有利な税制がたくさん設けられているからです。
たとえば、資本金等が1,000万円超になると地方税の均等割が上がりますし、3,000万円を超えると投資促進税制等の税額控除が利用できなくなります。
なかには、「うちの会社が赤字だから、節税対策は必要ない」と考える経営者もいるかもしれません。確かに赤字であれば所得に対してかかる税金は発生しませんが、その赤字は翌期以降に繰越すことができるので、将来の黒字と相殺することができます(最大10年)。
つまり、たとえ今期が赤字であっても、中長期的な視点を持って毎年節税対策をすれば、将来黒字になったときに、会社により多くの資金を残すことができるのです。
節税対策は中長期的な視点で行う方が効果が出るものですし、どのような節税対策を行なえばよいのかは個々の状況によって異なります。したがって、早めに税理士に相談して節税対策のアドバイスを受けることをおすすめします。
決算前にできる節税対策
節税対策は、決算前に慌てて行うよりも中長期計画を立てて実行する方が、効果があるケースがほとんどです。
たとえば、子会社を設立して利益を分散することで法人税が軽減されることがありますし、社宅制度を導入すれば、会社の負担する家賃を経費として計上することができます。
しかし、これらの対策を決算前に実行するには難しいため、ここでは決算前でも検討できる節税対策についてご紹介します。
(1)締め後の給与の未払を計上する
給与については、支給日に損金に計上している会社が多いと思いますが、一定の要件を満たせば、締め後の給与を未払として計上し損金に算入できるケースがあります。
たとえば、給与の計算期間が15日締めで25日支払いとしている会社が12月決算の場合、12月16日から12月31日までの給与を当期の損金として未払計上することができます。
ただし未払費用が損金になるかは、その事業年度終了の日までに債務が確定している必要があります。したがって、債務が確定しているということを主張するために、あらかじめ給与規定で計算期間や支給日を給与規定で規定しておくようにしましょう。
給与の場合には、仮に1月1日に従業員が会社を辞めたとしても実際に働いた期間(12月16日から12月31日まで)については、1月25日に支払わなければなりませんから、この場合には未払いの給与を損金算入することができます。翌期以降同様の処理を行うので初年度のみの節税対策とはなりますが、もしこのようなケースがあれば、未払費用として計上することを検討してみましょう。
(2)社会保険料の未払を計上する
健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けた額が月額保険料となり、これを会社と従業員が折半して負担することになっています。
社会保険料の会社負担分は支払日に損金としている会社が多いと思いますが、社会保険料は当月分を翌月末納付することになっています。
そこで、当月分の社会保険料は未払計上することで損金に算入することができます。
(3)短期前払費用を活用する
前払費用とは、リース料や地代家賃、保険料など会社が継続的に提供を受けるために支出した費用のうち、事業年度終了時においてまだ提供を受けていない部分に該当する費用をいいます。
たとえば、家賃は当月末までに翌月分の支払いをするケースがほとんどですが、このような場合の家賃の支払いは前払費用になります。
前払費用は、原則として「役務の提供を受けた時」に損金に算入しますが、一定の要件に該当するものは「短期前払費用」として支出時に損金に算入することができます。
|
短期前払費用となる要件
①支払った日から1年以内に提供を受ける役務であること |
たとえば、月払いの家賃を年払いにして決算時に損金に算入すれば、それだけ損金を増やすことができるので大きな節税効果が得られます。
ただし、いちど年払いとした場合には、その後も継続的に年払いとする必要があります。
したがって短期前払費用を活用する時には、「翌期も年払いの契約にしても、資金繰りに影響がないか」について検討する必要があります。
(4)貸倒損失を計上する
貸倒損失とは、売掛金や受取手形、売掛債権などが回収不能になった時に計上される費用です。
貸倒損失は要件が厳密に決められていて、①法律上の貸倒れ、②事実上の貸倒れ、③形式上の貸倒れの3つのケースのいずれかに該当する必要があります。
|
①法律上の貸倒れ 会社更生法、民事再生法などの規定に基づく認可決定によって切り捨てられることになった部分や、債務者の債務超過の状態が相当期間継続しており、その債務者に対して書面によって明らかにされたものなど ②事実上の貸倒れ ③形式上の貸倒れ |
なお、貸倒損失は計上するタイミングが大変重要で、回収できないことが明らかになった事業年度で計上しなければなりません。機を逸してしまうと貸倒損失が否認されてしまうので、注意してください。
(5)棚卸資産の評価損を計上する
在庫を保有する会社では、毎期必ず棚卸をしますが、この時帳簿棚卸の数量と実地棚卸の数量に差異がある場合や、商品の時価が取得価額より下がってしまったりした場合には、損失計上することができます。
|
棚卸資産の損失計上ができるケース
①決算日において、帳簿棚卸高と実地棚卸高との数量に差異がある場合 |
なお、棚卸資産の評価損益についてはそもそも認識をしないものとするのが原則ですが、以下の場合には評価損の計上が認められます。
|
評価損の計上が認められるケース
①災害によって、資産が著しく損傷したこと |
棚卸帳簿と実地棚卸との差異分析が可能になり、以上のような要件に該当した場合には、評価損を計上することで節税効果が期待できますので、検討してみましょう。
(6)固定資産の評価損を計上する
前述したとおり、棚卸資産については一定の要件に該当する場合には評価損を計上できますが、固定資産についても、これと同様に評価損を計上することができます。
評価損を計上できる要件は、災害によって損傷した場合、その資産が1年以上にわたり遊休状態である、その資産の所在する場所の状況が著しく変化した、など一定の場合に限られますが、要件を満たさない場合でも、除却損の計上や増加償却など、さまざまな規定がありますので、検討する価値は十分あります。
また、繰延資産についても、一定の要件に該当する場合には評価損の計上が認められています。
(7)決算期を変更する
「急に利益が出ることになった」という時に使える節税が決算期変更という方法です。
決算期を変更することで、今期の決算で多額の納税をする必要はなくなり、約1年の猶予期間ができることになりますから、その猶予期間の間に節税対策を実行していくことができます。
なお、決算期の変更をした場合には、所轄の税務署に異動届出書を提出する必要があります。
資金繰りが苦しいときは
これまでご紹介したような節税対策を行っても資金繰りが厳しく、納税額の用意が難しいこともあります。その場合には、仮決算や法人税の申告期限の延長を検討してみましょう。
(1)仮決算を検討する
前期の法人税の年税額が20万円(前期が12カ月の場合)を超える場合には、中間申告が必要になります。
この中間申告には①「予定申告」と②「仮決算」の2種類があります。
|
①予定申告
前期の実績をもとに計算する方法で、前期の法人税の年税額を前期の事業年度の月数で割って6を乗じて計算します。たとえば、前記の事業年度が12カ月、年税額が30万円の場合には納税額は「30万円÷12×6=15万円」となります。 ②仮決算 当期開始日からの6カ月間を1事業年度とみなし、通常の決算と同じように決算を行なって、税額を計算する方法です。ただし、仮決算の結果予定申告の金額を超える場合には、予定申告を行うことになります。 |
前期にたまたま大きな利益が出たような場合には、当期の予定申告による納税額が多額になることがあります。このような事情があり資金繰りが厳しくなることが予想される場合には、仮決算を検討してみましょう。
(2)法人税の申告期限は延長できる
法人税の申告書は、通常事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に提出しなければなりません。
ただし、定款などで「毎月事業年度終了の日の翌日から2カ月以内には、定時総会が招集されない状況にある」と認められる時には、提出期限を1カ月延長することができます。
延長申請書は、所轄の税務署、都道府県税事務所および市区町村役場に、適用を受けようとする事業年度終了の日までに提出する必要があります。
なお、延長申請書を提出する際には、定時総会が事業年度終了の日の翌日から3カ月以内に開催することを証明するために定款を添付する必要がありますので、あらかじめ定款にその旨の文言が記載されているか確認しておきましょう。
まとめ
以上、決算前に検討できる節税対策についてご紹介しました。
節税対策はそれぞれの会社の資本金の額や売上高、業種によって異なります。また、効果的な節税対策だと思って実行してもリスクばかり大きくてほとんど効果がない節税対策もあります。
どの節税対策がよいのかについては、経営状況や取引先の状況を正確に把握しなければなりませんし、有効な対策について取りこぼしがないように実行する必要があります。
したがって決算間際ではなく、なるべく早い段階で税理士に相談することをおすすめします。
決算前の節税対策について相談する
freee税理士検索では数多くの事務所の中から、決算前の節税対策について相談できる税理士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
\ 節税対策について相談できる税理士を検索 /
この記事の監修・関連記事

監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
クラウド会計ソフトの「クラウド会計ソフト freee会計」が、税務や経理などで使えるお役立ち情報をご提供します。
「クラウド会計ソフト freee会計」は、毎日の経理作業を最小限で終わらせることができるクラウド型会計ソフトです。疑問点や不明点は、freee税理士検索で税理士を検索し、決算前の節税対策について相談することができます。






