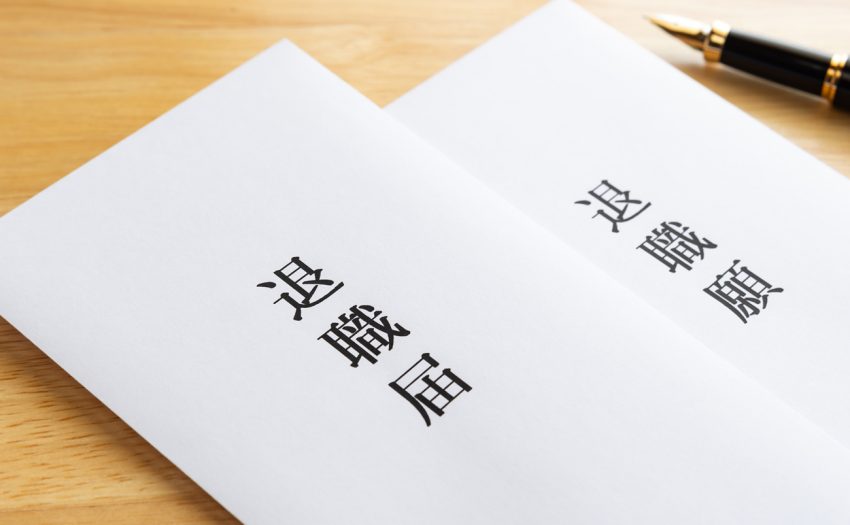社会保険とは|令和4年(2022年)10月の改正とは
公開日:2019年12月16日
最終更新日:2022年07月12日

目次
この記事のポイント
- 社会保険制度には、「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」がある。
- 「狭義の社会保険」とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つ。
- 令和4年10月以降、健康保険・厚生年金保険の適用が拡大される。
社会保険とは
社会保険とは、憲法で定められた社会保障のひとつです。保険という制度を利用して、疾病、ケガ、出産、失業、障害、老齢、死亡、要介護といった保険事故が起きた場合に、その人やその家族に対して必要な給付を行い、その生活や医療を保障することを目的としています。
(1)広義の社会保険と狭義の社会保険
社会保険制度には、「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」があります。
「広義の社会保険」は、「狭義の社会保険」と「労働保険」に2つに区分され、
「狭義の社会保険」とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つをいいます。
| 社会保険(広義) | 労働者保険 | 社会保険(狭義) | 健康保険 介護保険 厚生年金保険 |
| 労働保険 | 雇用保険 労災保険 |
||
| 一般国民保険 | 国民健康保険 国民年金 |
||
社会保険は、働き方などによって加入する社会保険が異なります。
また、運営するために保険料を徴収したり保険給付を行ったりする運営主体や実際に業務を行う管轄先も以下のように異なります。
|
①労災保険 労働基準監督署 労災保険給付の申請や労働保険料の申告などは、管轄の労働基準監督署で行います。 |
|
②雇用保険 公共職業安定所(ハローワーク) 給付金の請求や助成金の申請、資格取得届の提出、資格喪失届の提出などは、管轄のハローワークで行います。 |
|
③健康保険・④介護保険 全国健康保険協会(協会けんぽ)、年金事務所、健康保険組合 健康保険の給付に関する手続きは、協会けんぽです。 健康保険の申請は年金事務所が窓口となります。 健康保険組合に加入している会社の健康保険の窓口は、健康保険組合が窓口となります |
|
⑤厚生年金保険 年金事務所 年金に関する諸手続きや相談は年金事務所が窓口です。 |
(2)社会保険は強制適用が原則
社会保険制度は、お互いに助け合う制度という意味から、強制適用が原則です。
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)については、株式会社などの法人はすべて強制適用です。また、個人事業主の場合でも、一定の業種(農林水産およびサービス業)以外は強制適用です。
労働保険(労災保険・雇用保険)についても、一定の業種(農林水産業)などをのぞいては1人の労働者を雇用した場合に強制適用となります。
| 法人 | 個人 | ||
| 社会保険(狭義) | 健康保険 介護保険 厚生年金保険 |
◎強制適用 | △適用業種など一定の要件に該当したら強制適用 |
| 労働保険 | 雇用保険 労災保険 |
◎強制適用 | 〇1人でも労働者を雇用したら強制適用 |
(3)役職による社会保険の加入義務
労災保険は労働者を対象としているため、原則として、会社役員や自営業者などは加入することができません。しかし例外的に、労働災害のリスクが高い業務内容の場合であれば、労働者ではなくても一定の補償が得られる場合があります。
| 雇用保険 | 労災保険 | 健康保険 | 厚生年金保険 | |
|---|---|---|---|---|
| 代表取締役 | × | × | 〇 | 〇 |
| 取締役 | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 従業員 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(4)社会保険の加入は事業主が行う
従業員が社会保険に加入するときには、事業主である会社が手続きを行います。
健康保険と厚生年金保険の被保険者資格取得の届出
従業員が入社したら、健康保険と厚生年金保険の被保険者資格取得の届出を行い、交付された健康保険被保険者証を従業員に渡します。
健康保険被保険者証は交付されるまでに一定期間かかりますので、交付されない間に従業員が病院に行く場合には「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を準備する必要があります。
「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」は、資格取得の届出を行う時に作成し、年金事務所または事務センターに提出して押印してもらうことで、健康保険被保険者証の代わりに病院に提出します。
雇用保険と労災保険
雇用保険については、入社した従業員の資格取得の届出を行います。
パートやアルバイトでも、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用されることが見込まれる等、一定の要件を満たす場合には、雇用保険の対象となります。
労災保険は、自動的に労働者全員が対象となりますが、雇用保険の被保険者となるためには、別途手続きが必要となります。
労災保険は、従業員を雇用したら、労働基準監督署で加入手続きを行います。
手続きには、法定の申請書類と会社の登記簿謄本(登記事項証明書)が必要となります。労災保険手続きは、一度届出をすれば、次に従業員を雇用する時には手続きは不要です。
(5)保険料は事業主と被保険者で分担する
保険料を誰が負担するかは、保険の種類によって異なります。労災保険は事業主のみが負担します。
その他の保険は、事業主と被保険者が分担して負担します。被保険者が負担する保険料は、給与や役員報酬から天引きする形で事業主が徴収して、払込を行います。
したがって、給与計算業務の担当者は、給与計算業務の一環として社会保険料の計算を行う必要があります。
令和4年10月|健康保険・厚生年金保険が適用拡大
2022年(令和4年)10月から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されました。また、「特定適用事業所」の要件も変更となります。
参照:日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
| 対象 | 要件 | 平成28年10月~(現行) | 令和4年10月~(改正) | 令和6年10月~(改正) |
|---|---|---|---|---|
| 事業所 | 事業所の規模 | 常時500人超 | 常時100人超 | 常時50人超 |
| 短時間労働者 | 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし | 変更なし |
| 賃金 | 月額88,000円以上 | 変更なし | 変更なし | |
| 勤務期間 | 継続して1年以上使用される見込み | 継続して2カ月を超えて使用される見込み | 継続して2カ月を超えて使用される見込み | |
| 適用除外 | 学生ではないこと | 変更なし | 変更なし |
(1)「特定適用事業所」の要件が変更
「特定適用事業所」の要件については、2022年(令和4年)10月、令和6年10月に以下のように変更されます。
|
変更前 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所 令和4年10月からの改正 令和6年10月からの改正 |
健康保険組合には、毎月1回、年金機構から特定適用事業所の該当・不該当情報が報告されます。
事業主は、適用事業所が特定適用事業所となったときは、5日以内に、「健康保険・厚生年金保険特定適用事業所該当/不該当届」を日本年金機構又は健康保険組合に届け出る必要があります。
(2)「短時間労働者」の要件が変更
「短時間労働者」の要件については、2022年(令和4年)10月に以下のように変更されます。
※「短時間労働者」については、令和6年10月からの改正はありません。
|
変更前 雇用期間が1年以上見込まれること 令和4年10月からの改正 |
(3)改正に伴う影響と必要な手続き
令和4年10月に健康保険・厚生年金保険が適用拡大されたことで、社会保険料の企業負担額が増加する可能性があります。
従業員の社会保険料は、従業員と会社が折半で負担することになりますので、対象となる従業員が増えれば、必然的に会社が負担する社会保険料も増加するからです。
また、「扶養の範囲内で働きたいから社会保険に加入したくない」と思っている従業員の場合には、適用要件に該当しないよう労働条件の変更を申し出てくる可能性もあります。
短時間労働者で、被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認するとともに、労働力が減るか、減った場合にはその労働力を補充する際のコストも計算しておくようにしましょう。
まとめ
狭義の社会保険は、健康保険、厚生年金保険のことで、協議の社会保険と労災保険と雇用保険を含めて広義の社会保険といいます。
労災保険は、従業員をひとりでも雇用したら届出を行う必要があります。
雇用保険は、加入用件を満たす従業員を雇用するたびに届出が必要になります。
また、正社員はかならず健康保険、厚生年金保険に加入しなければならず、パートやアルバイトでも、勤務時間、勤務日数を基準として加入しなければならないケースがあります。
加入要件を満たす場合には、もれなく手続きを行うようにしましょう。
税理士・社会保険労務士をお探しの方
freee税理士検索では数多くの事務所の中から社会保険について相談できる税理士や社会保険労務士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
社会保険について相談できる社会保険労務士をさがす
この記事の監修・関連記事

監修:「クラウドfreee人事労務」
クラウドソフトの「クラウドfreee人事労務」が、人事労務で使えるお役立ち情報をご提供します。
「freee人事労務」は、複雑な労務事務を一つにまとめて、ミス・作業時間を削減します。法律や給与計算が分からないといったケースでも、ご安心ください。「使い方がわからない」「正しいやり方がわからない」をなくすための充実の導入サポート体制で、しっかりとご支援します。
また、人事労務に関する疑問点や不明点は、freee税理士検索で社会保険労務士や税理士を検索し、相談することができます。
クラウド会計ソフト freee会計