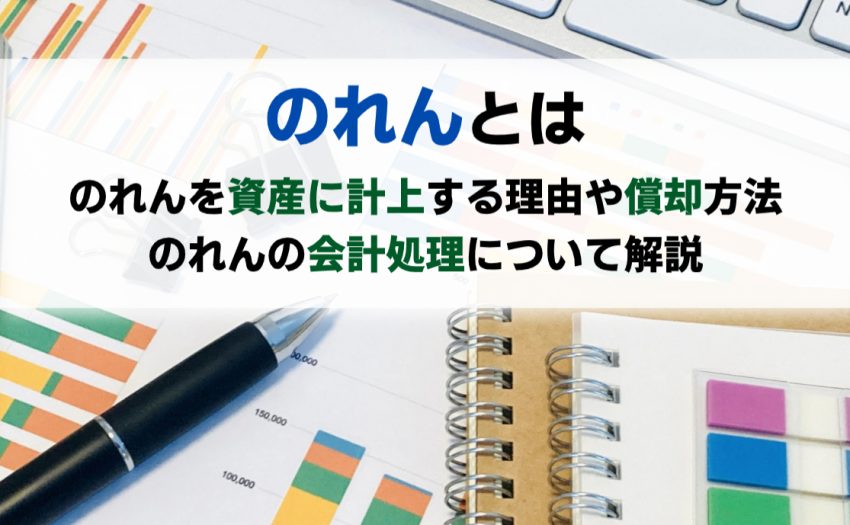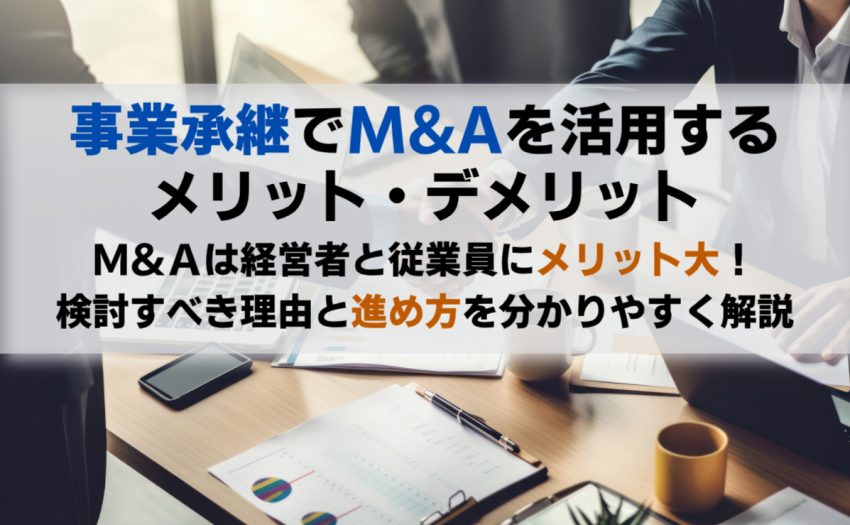空き家特例の3,000万円控除とは
公開日:2019年11月28日
最終更新日:2024年02月02日
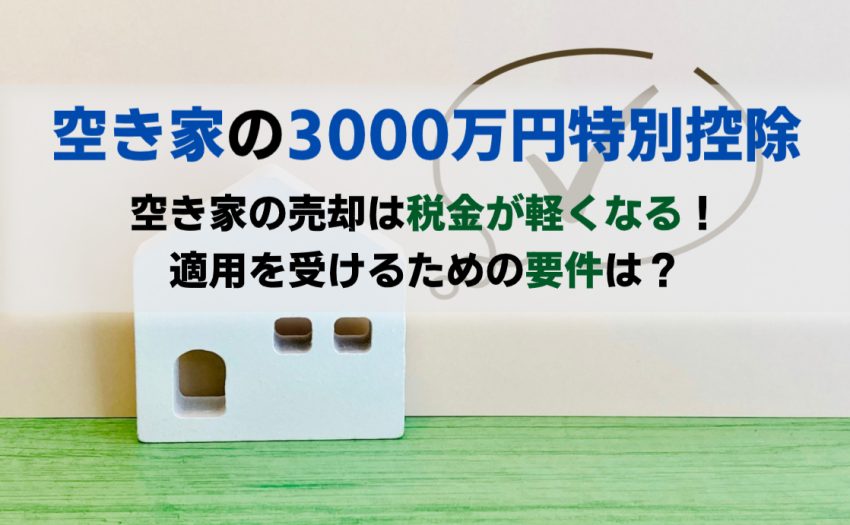
目次
この記事のポイント
- 空き家特例とは、空き家を相続した時の特例。
- 空き家特例は、適用期限が4年間(令和9年12月31日)延長された。
- 空き家特例を受けるためには、確定申告等が必要。
空き家特例とは、平成28年度の税制改正によって新設された特例で「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」のことです。
この空き家特例が4年間(令和9年12月31日まで)、延長されました。該当する人はぜひ活用しましょう。
税務調査の豆知識
相続で空き家になった被相続人(亡くなった方)の家を売却した場合、その売却で得た利益から3,000万円を差し引くことができます(令和6年1月以降の売却から、相続人が3人以上なら2,000万円)。これを空き家の3,000万円特別控除といい、令和9年12月までの特例です。
適用を受けるためには、建物が一定の耐震基準を満たしている、売却金額が1億円以上、相続開始から3年目の12月までに売却する(令和9年まで)などの要件を満たしている必要があります。
さらに、一定条件を満たせば小規模宅地等の特例や居住用財産の買い換え特例と併用ができます。
適用を受ければ、税金を少なくすることができますので、ぜひ活用したいものです。
建物の主な条件や売却の主な条件、必要な手続きなどについては、税理士にお問合せください。
空き家を相続した時の特例とは
空き家を相続した時の特例、略して「空き家特例」とは、相続した家屋に耐震リフォームを行った後や古家を取り壊して更地にした後で売却したりした場合に受けられる特例です。
年々放置される空き家が増えて、治安の悪化や災害時の倒壊のリスクなど、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすケースが増えています。
このような空き家対策を進めるためには、所有者等が適切に空き家の除却などを行い、放置したままの空き家を抑制することが必要です。
そこで、空き家を売却しやすくするために設けられた特例が、空き家の3,000万円特別控除です。
(1)空き家特例の適用要件等が令和5年度改正
空き家特例については、令和5年度に改正され、適用期限が4年間延長されるとともに、適用要件の緩和および制限がされることになりました。
現状は、特例措置の対象となるのが、譲渡前の工事に限定されていて、工事の発注等に関する負担を理由として売主が空き家を放置するケースが問題視されていました。
この点の適用範囲が拡大され、譲渡後に買主が工事を行う場合でも、特例の対象となることとなりました。
また、令和5年度の改正により、相続人が3人以上の場合には特別控除額が2,000万円に引き下げられることとなりました。
(2)空き家特例はなぜおトクか
空き家特例は、売却した場合の譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。譲渡所得から3,000万円を差し引くことができれば、税額が大きく軽減されることになります。
| 譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(3,000万円or2,000万円) |
|---|
(2)空き家特例の適用期限が令和9年まで延長
空き家特例は、当初は令和元年12月31日までとされていましたが、令和5年12月31日までに延長されました。
そして、令和5年度の改正によって、適用期限がさらに4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長されることになりました。
この特例は、少子高齢化や災害によって空き家が増加傾向である状況に関する対策なので、さらに延長される可能性があります(2024年2月現在)。
(3)空き家特例の要件(令和5改正)
空き家特例を受けるためには、いくつかの要件があります。
相続した家屋については、被相続人が亡くなった時にその家に住んでおらず、老人ホームなどに入居していた場合も対象となります。
| 項目 | 内容 |
| 家屋の要件 | 以下の要件に該当する被相続人居住用家屋 ①相続開始の直前まで、被相続人が1人で居住していたこと(一定の要件で老人ホームに入居していた場合も対象)。 ②昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること。 ③相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと。 ④相続によって土地および家屋を取得すること。 ⑤譲渡対価の額の合計額が1億円以下であること。 |
| 対象者 | 相続の開始直前に、被相続人が住んでいた家屋およびその敷地等である土地等を相続または遺贈によって取得した相続人 |
| 譲渡時期 | 平成28年4月1日~令和9年12月31日までの譲渡(令和5年度改正により、4年間延長)で、その譲渡が相続が開始した日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までのものであること。 |
| 譲渡の内容 | ①改修工事をした後に譲渡する場合 ・相続時から譲渡時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと。 ・譲渡時において、一定の耐震基準に適合していること。 ②被相続人居住用家屋の除却、全部の取り壊しまたは滅失後に被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡する場合 なお、令和5年度の改正によって、令和6年1月1日の譲渡については、譲渡時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、以下の要件に該当する場合には、本特例が適用できることとなりました。 |
| 手続き | 特例の適用を受けるためには、特例の適用を受ける年分の確定申告書に必要事項を記入し、所定の書類を添付する必要があります。 |
| その他 | ①相続財産を譲渡した場合の取得費の特例との併用不可。 ②同一の被相続人から相続または遺贈によって取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等について、本特例の適用を受けていないこと。 ③親子や夫婦など特別な関係にある人に譲渡していないこと。 |
(4)空き家特例の適用の制限(令和5改正)
空き家特例については、令和5年度の改正によって、相続または遺贈による被相続人居住用家屋、および被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合に、特別控除額が2,000万円に引き下げられることとなりました。
| 相続人の数 | 改正前の特別控除額 | 改正後の特別控除額 |
| 2人以下 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 3人以上 | 3,000万円 (3人の場合の限度額9,000万円) |
2,000万円 (3人の場合の限度額6,000万円) |
(5)空き家特例の特別控除を受けるための手続き
空き家特例の特別控除を受けるためには、市区町村に「被相続人居住用家屋等確認書」を申請し、確定申告の際に提出する必要があります。
被相続人居住用家屋等確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」は、空き家の所在地の市区町村で申請します。確認書の交付のためには、以下の書類の提出が必要です。
|
被相続人居住用家屋等確認書申請の際の必要書類
①被相続人居住用家屋等確認申請書 |
確定申告
確定申告は、譲渡翌年に行います。
交付された被相続人居住用家屋等確認書のほか、譲渡所得の金額に関する計算の明細書、登記事項証明書などが必要です。
|
確定申告の際の必要書類
①被相続人居住用家屋等確認申請書 |
まとめ
空き家特例とは、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」のことで、空き家を相続した場合に3,000万円または2,000万円の特別控除を受けることができます。
空き家特例は令和9年12月31日までに延長されましたので、該当する人はぜひ活用して税額を軽減させましょう。
空き家特例について相談する
freee税理士検索では数多くの事務所の中から、空き家特例について相談できる税理士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
\ 空き家特例について相談できる税理士を検索 /
この記事の監修・関連記事

監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
クラウド会計ソフトの「クラウド会計ソフト freee会計」が、税務や経理などで使えるお役立ち情報をご提供します。
「クラウド会計ソフト freee会計」は、毎日の経理作業を最小限で終わらせることができるクラウド型会計ソフトです。疑問点や不明点は、freee税理士検索で税理士を検索し、空き家特例の活用や確定申告、節税対策について相談することができます。