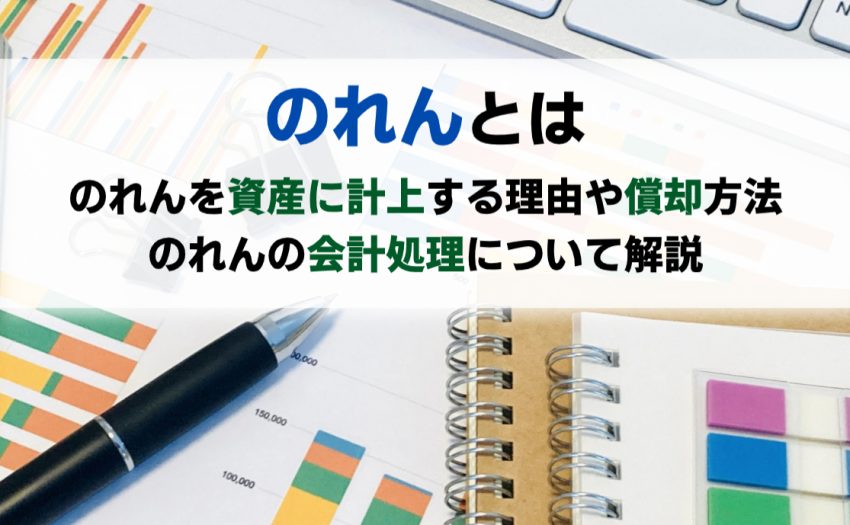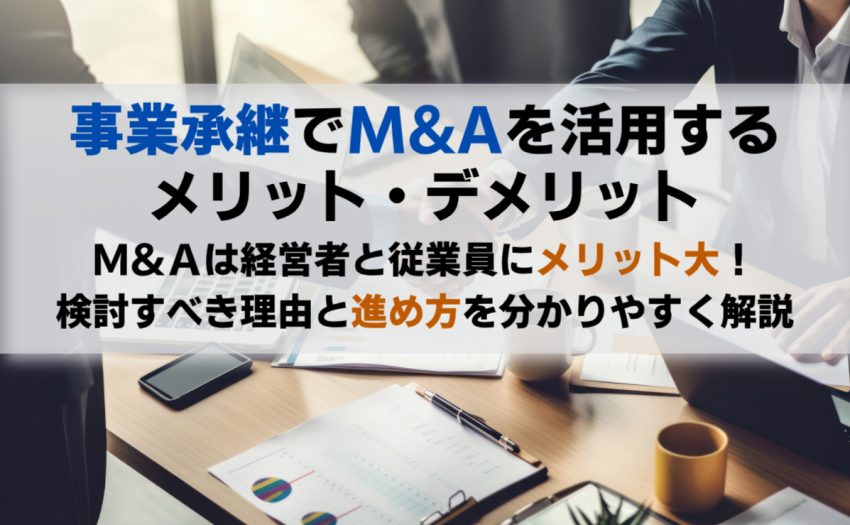税務調査の立ち会いを税理士に依頼するメリット
公開日:2018年10月31日
最終更新日:2024年02月01日
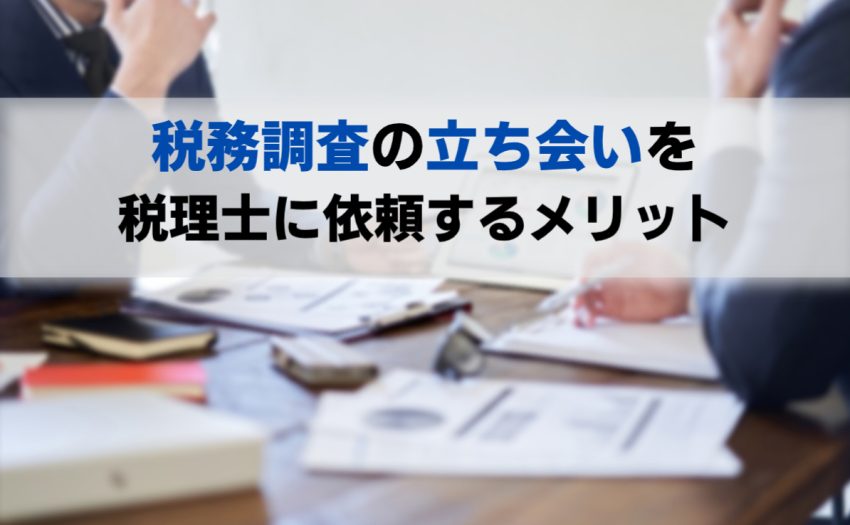
目次
この記事のポイント
- 税務調査は、税理士に立ち会ってもらうことができる。
- 税理士に依頼することで、税務調査に必要が準備をすることができる。
- 修正申告が必要になった時も、税理士がいればスムーズに対応が可能となる。
税務調査は、納税者が申告した申告内容について調査を行い、違法な処理や誤った処理がある場合には、税法に従った申告や納税に修正させるために行われます。
税務調査には大きく分けて「強制調査」と「任意調査」があり、ドラマや映画などでよく見る税務調査は「強制調査」です。
中小企業や個人事業主の場合に行われる税務調査は、ほとんどのケースで任意調査であり、強制調査の対象となることはまずありません。
ただし任意だからと言って、原則として調査を拒否することはできません。拒否するとかえって『怪しい』と疑われてしまいます。
納税の義務がある会社や個人事業主にとって、税務調査は避けることができないものと捉え、しっかり対応するようにしましょう。
税務調査の豆知識
申告書に「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」が添付されていると、その申告書は資格のある税理士によってしっかり検査されたものであることを示します。また、この書面が添付されていると、税務署は原則として調査に着手する前に税理士に対して申告書上の疑問について質問する機会を与えなければならないことになっています。そして、税理士の説明で疑問点が解消し、調査官が税務調査は必要ないと判断すれば、実地調査は行われません。
つまり、申告書を税理士に作成してもらい、申告書に「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」を添付してもらえば、税務調査の対象となりにくいというメリットの他に、税理士が先にしっかりと説明し調査官を納得させてくれれば実地調査が行われない可能性が高いというメリットも期待できるのです。
そもそも税務調査とは
税務調査とは、納税者が申告した申告内容を確認するための調査のことをいいます。
調査の結果、違法な処理や誤った処理がある場合には、税法に従った申告や納税に改めさせなければなりません。
税務調査には大きく分けて「強制調査」と「任意調査」があります。
税務調査というと、ある日突然会社に大勢の調査官がやってくるシーンをイメージする人が多いようですが、それは国税局が行う強制調査であり、悪質で計画的な不正に対して、裁判所からもらった捜査令状をもとに行われる調査です。
中小企業や個人事業主の場合は「任意調査」であるケースがほとんどで、税務署が申告内容についてそれほど疑問を持っていないケースです。
事前に会社か顧問税理士に連絡があり、会社の承諾を得てから調査日が決定し、当日は帳簿や請求書などの書類を中心に、調査が行われます。
「税務調査」という場合には、一般的にこの任意調査を意味しますので、ここでも任意調査についてご紹介します。
(1)税務調査の目的
税務調査の目的は、提出された法人税及び消費税申告書が、事実に基づいているか、正しく作成されているかを確認することにあります。
納税者の税務処理をチェックして、脱税や税務上の誤りがあれば、指導や摘発を行い、追徴課税を行います。
日本は、納税者が納税額を計算し納税する「申告課税方式」をとっていますが、もし、税務調査がなかったら税金をごまかす人と真面目に申告納税する人に税負担の不公平が生じてしまうこともあるでしょう。
その意味で、税務調査は大変重要かつ必要な調査であるといえます。
税務調査というと、良いイメージを持つ人はあまりいないようですが、伝票・帳簿類、帳票や契約書、領収書などの書類を日頃からしっかり整理し保管をして真面目に申告をしていれば、税務調査の対象となってもしっかりと主張することができますので、とくに怖い調査ではありません。
(2)税務調査の主な流れ
税務調査は、次の手順で実施されます。
|
①調査対象会社の選定 税務署の調査官が、調査対象となる会社を決定します。 「売上が上がっているのに所得が上がっていない」「一定の勘定科目(経費)が、昨年と比べて増え過ぎている」「事業規模が変わった」「内部告発があった」などといった事情がある場合に、対象の会社に選ばれます。 調査対象に選ばれるサイクルは通常は3年~5年という会社もあれば、6~7年という会社もあります。また、創業以来1度も税務調査の対象となったことがない会社もあれば、毎年のように税務調査の対象となる会社もあります。 ②調査の連絡 ③調査実施 ④発見事項の説明 ⑤修正申告書の提出と納税 |
(3)税務調査はどのくらい行われている?
税務調査が行われる会社の件数について、令和5年11月に国税庁から発表された調査実績によると、
実地調査が行われたのは6万2,000件、簡易な接触事積(書面や電話による連絡や来署依頼による面接など)は、6万6,000件となっています。
【実地調査件数】
【簡易な接触事積】
|
税務調査を税理士に依頼するメリット
税務調査の連絡がきたら、必ず税理士に立ち会いを依頼しましょう。
税理士なら、過去の決算書を見るだけで、税務署から指摘されそうな問題点の目星をつけることができます。そして、その部分について必要な対策を行うことができます。
また、調査当日に立ち会ってもらうこともできます。
(1)事前に準備ができる
税理士に依頼すれば、税務調査の際に調査官が、帳簿のどの点に疑問を持ちそうか、どの点を重点的に調査しようとしているかについて、あらかじめ把握することができます。そして、その点について当日しっかり説明ができるように準備を進めることができます。
なお、通常の会社の場合には、調査を受ける時に準備をしておいた方がよい書類は、3期分の帳簿、請求書や領収書、見積書などの書類となります。
必要となる書類、準備した方がよい書類は、個々の会社の状況、取引先の状況などによって異なりますので、この点も税理士に相談するようにしましょう。
税務調査で準備する書類
|
(2)税務調査当日に立ち会ってもらえる
税理士には、税務調査当日に同席を依頼することができます。
当日は、税務調査官に、事実の有無(事実認定)と税務上の解釈の両方について、質問されます。
事実の有無については社長か経理担当が回答する必要がありますが、税務上の解釈は、税理士から回答してもらうようにしましょう。
たとえば、ある料亭で行った会食の領収書が問題になったとします。
この時調査官に、「誰と誰がこの料亭に行ったのか、どのような話をしたのか」と質問されたら、社長か経理担当は、領収書に記載されたメモを見ながら説明し、どのような理由で会議費に計上したかを回答します(事実認定)。
そして、その結果を受けて「会議費に該当するか交際費に該当するか」といった説明は、税理士に任せることになります(税務上の解釈)。
(3)税務調査後の修正申告に対応してもらえる
問題点が全く発見されないケースもありますが、調査官に問題点を指摘された時には、事実認定の部分に誤りがないかを確認し、税理士と相談します。
発見された問題点を認める場合には、税理士が修正申告書を作成します。
そして、修正申告書の税額に従って、税額を納付します。
税務調査を税理士に依頼する際のQ&A
税務調査を税理士に依頼する場合には、「どのくらいの費用がかかるのか」「顧問税理士がいない場合でも、対応してくれる税理士がいるのか」など、不安や疑問をお持ちの方もおおいと思います。
ここでは、税務調査を税理士に依頼する際のよくあるご質問についてご紹介します。
(1)税務調査の税理士費用の相場は?
2002年(平成14年)の税理士法改正によって、税理士会の報酬規程が廃止され、税理士が独自に決めた報酬規定が作成されるようになりました。
したがって、現在は税務調査の立会いについての報酬についても、個々の税理士事務所によって異なりますが、報酬の額については、旧税理士報酬規定を参考にしている税理士事務所が多いため、ここでも旧税理士報酬規定の報酬についてご紹介します。
旧税理士報酬規定では、税務調査の1日あたりの報酬は、60,000円となっています。
また、遠方の税理士に依頼する時には、日当、旅費、宿泊費なども負担しなければなりません。
旅費や宿泊費は、実費ですが、日当について、旧税理士報酬規定では、1日あたり50,000円となっています。
(2)顧問税理士がいない時は?
顧問税理士がいない場合でも、税務調査から対応してくれる税理士もいますので、ぜひ税理士に立ち会ってもらうことをおすすめします。
税務調査においては、税理士の対処次第で調査結果に影響が出ることがあります。
税務調査に精通している税理士ならば、質問にどのように回答すべきか熟知していますので、反論すべき点、了承すべき点のメリハリをつけて調査官と交渉し、できるだけ短時間で調査を終了し、修正がないようにしてもらうことが可能となるからです。
とくに税務調査が初めてだという場合、予め税務調査の流れを教えてもらって事前に練習をしておけば、当日必要以上に緊張せずに済むのではないでしょうか。
まとめ
以上、税務調査の基礎知識や主な流れ、税務調査を税理士に依頼するメリットについてご紹介しました。
税務調査というと、怖いイメージを持っている方も多いと思いますが、税務調査に精通した税理士に依頼して税務調査の正しい対応方法を知っておけば、税務調査で嫌な思いをすることはありません。税務調査前に必要な書類を整理して税理士と打ち合わせを行えば、税務調査当日は、経営者は事業の概況を答えることに集中し、調査官が帳簿のチェックを始めたら、あとは税理士に任せることもできます。
税務調査について相談できる税理士を探す
freee税理士検索では数多くの事務所の中から、税務調査について相談できる税理士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。
顧問契約を締結していない場合でも、対応してくれる税理士も多数いますので、1日も早く連絡をとることをおすすめします。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
\ 税務調査について相談できる税理士を検索 /

監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
クラウド会計ソフトの「クラウド会計ソフト freee会計」が、税務や経理などで使えるお役立ち情報をご提供します。
「クラウド会計ソフト freee会計」は、毎日の経理作業を最小限で終わらせることができるクラウド型会計ソフトです。疑問点や不明点は、freee税理士検索で税理士を検索し質問することができますし、税務調査について相談することもできます。