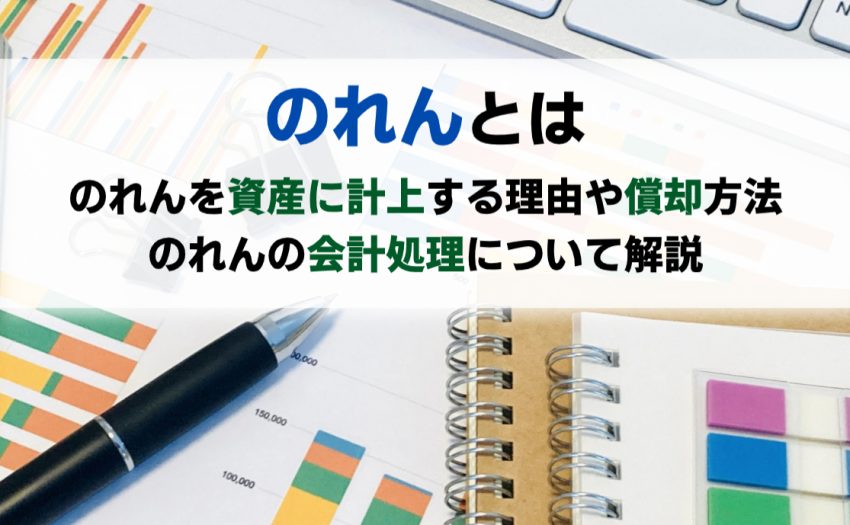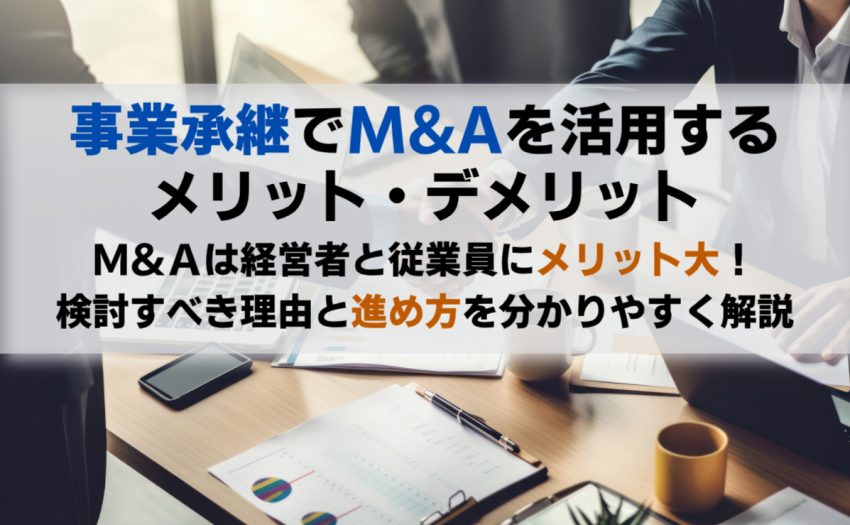税務調査の事前通知とは?どう対応すべきか
公開日:2018年10月31日
最終更新日:2024年03月15日
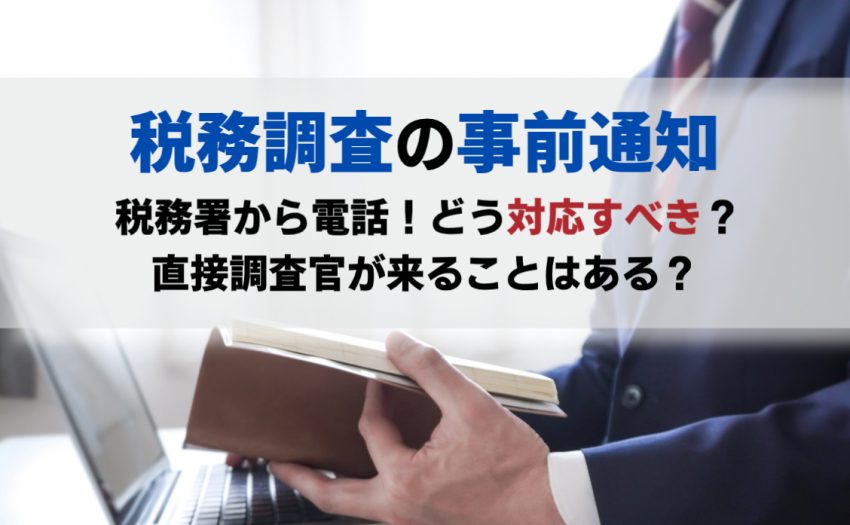
この記事のポイント
- 税務調査とは、税務署の調査官による調査のこと。
- 税務調査は1日で終わることもあるが、普通は2日程度行われる。
- 税務調査は通常は事前通知があるが、突然調査官がやってくることもある。
税務調査の対象となって、喜ぶ人はあまりいないでしょう。たいていは、「疑われているのか」とよい気持ちはしないものですし「何を調べるつもりなのか」と不安を感じることも多いでしょう。しかし、調査の前にしっかりと準備をして、税理士に相談し、当日どのような対応をすればよいかについて事前にアドバイスをもらっておけば、税務調査は何ら恐れるものではありません。
税務調査の豆知識
税務調査とは、国税庁や税務署が納税者から申告された申告内容について調査し、違法な処理があった場合には税法に従って申告や納税を改めさせるために行われる調査のことです。
税務調査の対象は必ずしも所得税、法人税だけというわけではなく、消費税、印紙税、固定資産税など事業にかかわるすべての税金の他、個人の相続税なども対象となります。
税務署は、納税者から提出された決算書や確定申告書について、事前に検討していて、「売上をごまかしているのではないか」「経費が昨年と比べると多すぎる」「相続財産にモレがあるのではないか」という疑問が生じた場合には「納税者のところに直接出向いて、調査してみよう」ということになり、税務調査は行われることになるわけです。
一般の任意調査の場合であれば、ほとんどのケースで税務署からの事前通知があります。
ただし、任意調査でも非常に厳しく調査されることもあり、これは「特別調査」と呼ばれます。社長の自宅や銀行、取引先に同時に調査が入ることもあります。これは、税務署が「悪質で複雑なケースである」と判断しているケースで、事前に通知がありません。
なお、前述したとおり「強制捜査」の場合も、事前通知はありません。ある日100人規模の優秀な調査官が会社に突然来て、徹底的に調べられることになります。
税務調査の事前通知と準備
税務調査の連絡は、ある日突然1本の電話から始まります。
「税務署から電話がきた!」というだけで、落ち着かなくなってしまう人もいますが、ここはまず落ち着いて即座に回答をしないことが大切です。そして、調査はできるだけ先送りにしましょう。たとえ、「やましいことはない」という場合でも、税理士には必ず立ち会ってもらう方が望ましいからです。
したがって、「税理士の立会いを望みますので、税理士の都合を聞いて、折り返し連絡をします」と回答するようにしましょう。
税理士の立会いがあるか、税務調査でどのように対応するかにより、大きく議論の方向性が変わっていくこともありますので、慎重に準備を行って臨むことが重要です。
(1)税務署から事前通知があった時の対応
税務署から税務調査に入る旨の通知がきたら、まず真っ先に顧問税理士に連絡を行い、相談しましょう。
顧問税理士がいない場合には、税務調査だけでも対応してくれる税理士もいるので、可能な限り早く相談するようにしましょう。
税務調査の前には、確認しなければならない事項や、準備しておかなければならない書類がたくさんあるので、可能な限り早めに面談のアポイントメントをとることをおすすめします。
そして、現在の会社の状況、書類整備状況などについて打ち合わせを行い、指摘されると考えられるポイントについて検討し、主張する内容、理由、税法上の根拠などを準備しておくようにしましょう。
(2)税務調査の事前通知なく突然来たら
任意調査でも、まれに事前に連絡がなく突然調査がくることがあります。
このような時にも、あわてずに落ち着いて対応することが大切です。
任意調査の場合には、会社は都合が悪い理由を伝えることで、税務調査の実施を断ることができます。
まず、税務署員の身分証明書を確認します。この時、顔写真と所属を確認することを忘れないでください。
そして、調査税目(法人税か消費税か、など)、何年分が調査対象なのか、調査の理由は何なのか、調査にかかる期間はどの程度なのかなどを確認してください。
そして、「税理士や他の重要な社員が同席できない」など、今すぐに税務調査を受けることができない旨を説明して、税務調査を別の日にしてもらうよう依頼しましょう。事前通知がない場合は、当然調査が行われても、調査のための準備ができていないものと思われますので、延期したほうが賢明といえます。
ただし、断ることができるからといって、法律上その税務署の権限に従わなかった場合には、罰則もあります。
つまり、会社は任意調査といえども実質必ず受けなければならず、その時点での税務調査は拒否することができても、無限定に延期することはできないということは理解しておきましょう。
なお、「強制調査(いわゆるマルサ)」の場合には、会社に突然調査に来ても、会社は拒否することはできません。
(3)税務調査で準備すべき書類は
税務調査では、準備しておくべき書類や資料がたくさんあります。
まず税務調査で必ず必要になるものとしては、指定された年度にかかわる税務申告書、そしてその申告書の元となる会計帳簿などが挙げられます。
また税務申告書を作成する上で必要となる各種算定根拠資料や、会計帳簿を作成する上で必要となる各種計算表や書類や証憑、規程なども用意しておくべきでしょう。
また、給与台帳なども調査の重要なポイントになります。最近では、これを悪用するケースも増えているので、調査官にチェックされやすい項目の1つとして、しっかり確認しておきましょう。
この他必要となる書類は税務調査の調査税目や調査の理由により変わりますので、税理士に細かくアドバイスをもらうことが必要です。
(4)税務調査の種類を知っておこう
日本の税務調査は大きく分けて「任意調査」と呼ばれる調査と「強制調査」と呼ばれる調査の二つの種類があります。
|
任意調査 一般に「税務調査」と呼ばれているものは、ほとんどが「任意調査」を意味し税務署の調査官によって行われます。 「任意」で行われる調査ではありますが、原則として拒否することはできないのが実情です。税務調査の対象となった納税者には、調査官の求めに応じて書類を準備したり質問に答えたりといった、真摯な協力が求められます。 強制調査 |
| 税務調査 | 任意調査 | 準備調査 | 主に税務署内で行われる調査 | 机上調査 | 申告書等を税務署内で調査する |
| 外観調査 | 対象とするか否かについて取引先や来客数、不動産の状態などを外観から調査する | ||||
| 書面調査 | 対象者に疑問点について文書で問い合わせをする | ||||
| 呼出調査 | 対象者を呼出して説明を求める | ||||
| 実地調査 | 実際に調査先に出向いて帳簿書類その他の物件を検査すること | 一般調査 | 帳簿調査が中心 | ||
| 現況調査 | 対象者の現況を知るために抜き打ちで行われる | ||||
| 反面調査 | 対象者の取引先や取引銀行に対して取引の実態調査を行う | ||||
| 特別調査 | 脱税など不正が行われている可能性があるが、一般調査だけでは確定できない場合に厳しく行われる調査 | ||||
| 特殊調査 | 一般調査だけでは不十分な場合に、グループ企業を含めて総合的に行われる調査 | ||||
| 強制調査 | 査察 | ||||
(5)なぜ税務調査の対象に選ばれたのか
税務調査は、個人事業主でも会社でも、納税義務がある以上は避けては通れないと思っていた方が無難です。通常の会社(納税意思もあり、申告内容も優秀な会社)では、3~5年のサイクル、長くても6~7年のサイクルで調査の対象になるケースが多いのですが、なかには「売上も利益もそこそこあるのに、これまで一度も税務調査の対象となったことがない」というケースもあります。
とはいうものの、税務署もくじ引きで税務調査の対象を選んでいるわけではなく、いくつかの基準をもとに税務調査の対象を決めています。したがって、税務調査の対象となりやすい場合もあれば対象とならない場合もあるわけです。
一般的にチェックされやすいのは「所得率」です。
毎期の所得率をチェックして所得率が年々下がっている場合には「利益圧縮して税金をごまかしているのではないか」として調査対象となりやすく、同業他社と比較して他社より低い所得率であれば、税務調査の対象となりやすくなると言われています。
また、追徴課税が多額に想定される会社は、調査対象に選ばれやすい傾向があります。
具体的には、「利益が多額に出ている会社」や「業績が好調な業界」「前期と比べて、財務状況や経営成績が大きく変動している会社」などです。
他にも「長期間税務調査が入っていない会社」や「税務に関する不正の兆候が見られる会社」なども調査対象となりやすくなります。
また、悪質な会社の場合は、毎年といっていいほど税務調査が行われることもあります。
令和5年11月に国税庁から発表された調査実績によると、実地調査が行われたのは6万2,000件、簡易な接触事積(書面や電話による連絡や来署依頼による面接など)は、6万6,000件であり、、申告漏れ所得金額は7,801億円、追徴税額は3,225億円、調査1件当たりの追徴税額は5,241,000円となっています。
【実地調査件数】
【簡易な接触事積】
|
また消費税還付申告法人に対しては、特に厳正な調査が実施されており、令和4年の法人消費税の実地調査は61,000件行われたとされています。
参照:国税庁「令和4事務年度法人税等の調査事績の概要(令和5年11月発表)」
(6)税務調査で行われる「反面調査」とは
税務調査においては、納税者だけでなく納税者の取引先や銀行で調査をし、証拠を収集することがあり、これを「反面調査」といいます。
反面調査は、納税者の調査だけでは、確たる証拠を得られないケースで行われますので、反面調査が実施されないようにするためには、日頃から契約書や請求書、領収書などを整理しておくことが基本です。調査過程で取引先との契約内容について十分な説明資料が足りなければ、取引先に資料の再発行を依頼する努力を条件に、調査官に反面調査はしないで欲しいと依頼してみましょう。
反面調査先は自社の調査でなくても、この反面調査には協力をしなければなりませんが、だからといって反面調査を無作為に行えば、納税者のビジネス環境を悪化させる可能性もあるため、反面調査されるデメリットを説明し、その代わりに責任を持って資料を備えることを約束すれば、調査官に納得してもらえる可能性はあります。
いずれにせよ、反面調査には厳しいルールが設定されており、納税者保護の規定も同時に備えられていることになりますので、税理士からもきちんと説明してもらえるよう依頼しましょう。
税務調査当日の流れ
税理士と打ち合わせを行い必要な準備を整えて、いよいよ税務調査当日を迎えたら、慌てず落ち着いて調査官の到着を待ちます。
なお、当日の姿勢は、議論の方向性や税務署職員の心証などに大きな影響を与えます。調査に対しては、基本は協力的に応対するようにしましょう。ただし、質問された以外のことをやたらと話さない方が賢明です。
(1)税務調査の主な流れ
調査官は、たいてい2名で訪問するのが普通です。
調査官にもいろいろなタイプがありますし、やり方もさまざまですが、最初は「暑いですね」といった事項の挨拶や、サッカーや野球の話など雑談から入ることも多いようです。
これは、調査官がお互いの緊張をほぐすためのコミュニケーションですが、単なる雑談というわけではなく、たわいもない質問のなかから、会社や従業員の状況などの情報を得て、税務調査でどこを重点的に調査すれば良いかの判断を行っていることもあります。
ですから、つい気持ちが緩んで、会社のいらぬことをペラペラと話してしまうことがないように注意を払わなければなりません。ひと通りの雑談が終了した後、税務署職員は、用意した書類を元に調査を進めていきます。時折質問が来ることがありますが、税理士に立ち会ってもらえば、税理士が対応してくれます。事前の打ち合わせで準備した内容にそって答えるようにしましょう。
(2)調査官にはきちんと「質問」しよう
税務署には「質問調査権」というものが与えられています。そしてこれを根拠に、税務署職員は様々な質問を会社の担当者に投げかけてきます。しかしながら、この「質問調査権」というものは制限があり、税に関する調査について必要な場合のみに限られています。
ですから、むやみにやたら会社の機密情報を明らかにする必要はありません。もし、あまり趣旨が明らかではないと思えるような質問が投げかけられた場合、本当にその質問が税の調査と関連しているのかと質問を投げかけることもできます。
そのようにして、調査官の質問の趣旨を明らかにし、答弁を慎重な内容とすることができます。ぜひ、質問をすることにより防衛をしていきましょう。
また、会社の税務調査の際には、社長個人に質問をされることもあります。
個人事業主でない場合には、会社は社長とは別の法律上の存在になるので、本来であれば社長個人とは分離して考えるべき存在ではあります。ですから、理論的に考えれば、会社の税務調査の際の、社長個人に関する質問は、質問検査権の枠外といえるのです。
しかし、だからと言ってまったく無視して良いかといったらそういうわけではありません。税務調査を行う際に、税法に準拠してないと思われる兆候を認識した場合は、その件に関しても追加調査を行うことができる旨が規定されているからです。
なお、社長個人に関する質問があった場合は、「その質問は、法人の税務調査にどのように関連しているのか」といった質問を行うことで、調査官をけん制できる場合があります。
(3)昼食、お茶は提供すべきか
税務調査の際、昼食、お茶を税務署職員に提供すべきかどうかという点ですが、お茶くらいは出しても問題ないでしょう。
しかし、昼食は提供すべきではありません。なぜなら、国家公務員法の規定により、税務署職員は利害関係者からの金銭、物品の贈与や接待を受けることが禁止されているからです。ですから「お昼はどうしますか」と聞いても「外食してきます」と言って、それを受けることはないと思いますが、エチケットとして声掛けするのは望ましいといえます。
(4)税務調査中に即答する必要はない
税務調査中は、税法の様々なトピックが議論となります。
調査官の質問に対しては即答をする必要はないので、安易につじつま合わせの回答をせず、事実をしっかりと把握し分からない点や不明点は調べてから回答するようにしましょう。
税務調査後には、訴訟となる可能性もゼロではありません。したがって、議論した内容について正確にメモを取っておきましょう。また、提出した書類の控えも保管しておき、詳細を後ほど説明できるように準備しておきます。
(5)税務調査は税理士に立ち会いを依頼する
税務調査中は、必ず税理士に立会いを依頼しましょう。
税法の微妙な解釈や税務署職員の理論的な主張についても、税法に精通している税理士が同席していれば、根拠を示しながら説明してもらうことができます。
ただし、最初の概況調査に関しては、税理士では説明ができないケースもあります。
その時には社長や担当者が説明を行う必要があります。税理士に説明を依頼する事項、社長や担当者が説明をする事項などは事前に確認し、当日はうまく連携して対応するようにしましょう。
税務調査後の流れ
税務調査が終了すると、税務署から指摘事項の一覧が提出されます。
調査官の指摘について同意するか同意しないかを検討し、お互いに確認していくための話し合いを「折衝」といいます。この折衝によって、納税の額に大きな差が出てくることもありますので、十分な注意が必要です。
事実関係や認識の違いがあれば、もう一度ていねいに説明をする必要がありますし、時には歩み寄りながら解決の方法を探ることになります。
調査官と話合ってもなかなか歩み寄れない時には、調査官の上司である統括官と面談させてくれるよう依頼するのも、ひとつの手です。
折衝の方針についても、税理士と相談しておきましょう。
(1)税務調査後①「申告是認」
税務調査の結果、まれではありますが、「申告是認」という結論が出されるケースがあります。これは税務署が税務調査を実施した結果、追徴課税を課すべきところがないという結論を出すことをいいます。
したがって申告内容に問題がないと言われたら、「申告是認通知書」を出してもらいましょう。
ただし、これはかなりレアなケースであり、多くの場合は、税務署が修正すべき又は指導すべきと考える事項が出てきます。
(2)税務調査後②「修正申告」
修正申告とは、すでに行った申告について税額が少なかった場合などに行うもので、納税者自らが手続きを行います。
まずは、税務署から提出された修正内容の一覧を税理士と確認します。どの修正内容を受け入れ、どの修正内容に対して反論していくかを決めていく必要があります。
修正申告を行えば多くの場合で追徴課税は発生しますが、税務調査を早期に終わらせることができます。
なお、税務調査によって修正申告をする場合には過少申告加算税が課せられる可能性がありますが、自ら修正申告を行った場合にはこれが免除されることになっています。
(3)税務調査後③「更正処分」
更正とは税務当局側が行う処分で、提出された納税申告書に記載された内容が税法の規定に従っていなかった時や税務調査したものと異なる時に、税務署長がその税務調査に基づき、申告書に関わる課税標準または税額等を修正することです。
修正申告は納税者自らが行う手続きで後から不服を申し立てることはできませんが、更正処分は税務当局側が行う処分であり、納税者は後から不服申し立てができるという点が異なります。
税務調査によって指摘事項が示された時には、修正申告を行うか拒否して更正処分を受けるか判断する必要がありますが、かならず修正申告をした方がよいというわけではありません。
税務署としては、修正申告をするよう勧めてきますが、それは主に以下のような理由からです。
|
①納税者に修正申告を提出させてしまえば、納税者は税務当局に「再調査の請求」や国税不服審判所に「審査請求」ができなくなることから、後々税務署の手間が省かれる。 ②青色申告者に関しては、更正した理由を付記して納税者に通知しなければならないため、税務署の手間がかかる |
したがって、どうしても指摘事項等に納得できない場合には、とことん争うのもひとつの手でしょう。
まとめ
以上、税務調査の概要や種類、税務調査で準備すべきことや、対応するうえでの注意点についてご紹介してきました。
税務調査にはいい印象を持たない人がほとんどですが、税務調査に精通した税理士に相談して必要な準備を行い、税務調査当日に立ち会ってもらえば、税務調査は乗り切ることができます。税務調査の通知が来たら、すぐに税理士相談して、必要な対策について話し合うことをおすすめします。
税務調査について相談できる税理士をさがす
顧問税理士がまだいない方は、無料で使える「freee税理士検索」で数多くの事務所の中から税務調査に対応してくれる税理士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
\ 税務調査について相談できる税理士を検索 /
この記事の監修者・関連記事

監修:「クラウド会計ソフト freee会計」
クラウド会計ソフトの「クラウド会計ソフト freee会計」が、税務や経理などで使えるお役立ち情報をご提供します。
「クラウド会計ソフト freee会計」は、毎日の経理作業を最小限で終わらせることができるクラウド型会計ソフトです。疑問点や不明点は、freee税理士検索で税理士を検索し質問することができますし、税務調査について相談することもできます。