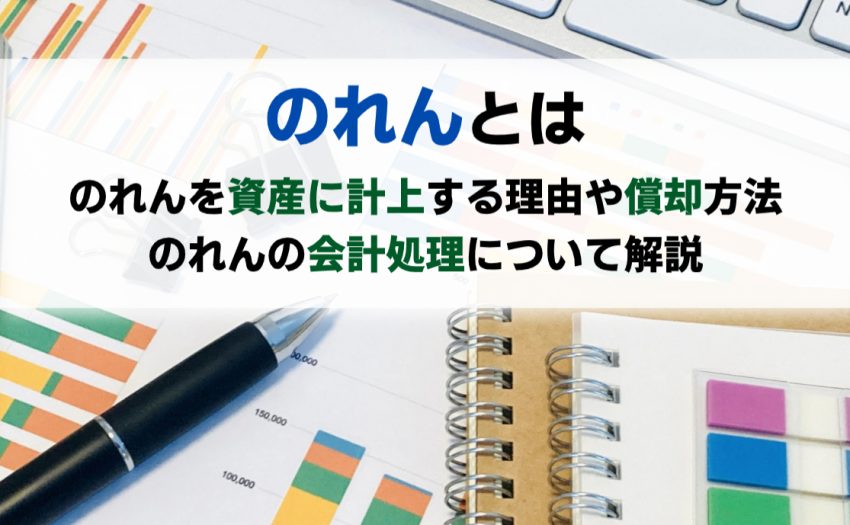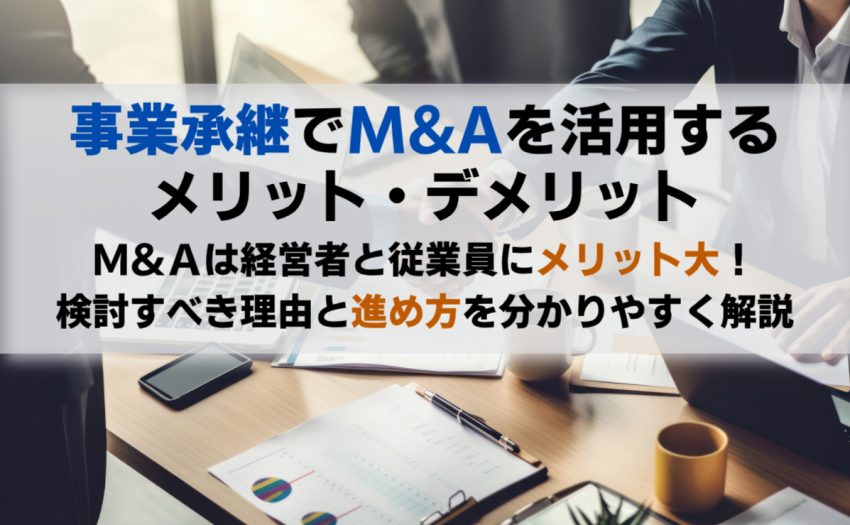会社員でも確定申告が必要な人・申告しないと損する人【2024年確定申告】
公開日:2018年10月30日
最終更新日:2024年03月11日
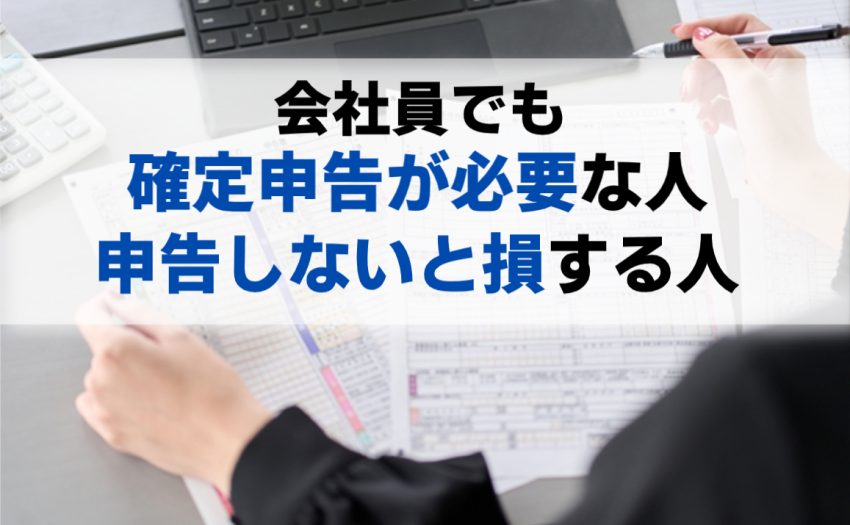
この記事のポイント
- 会社員でも、2カ所以上から給与をもらっている人や年収2,000万円超の人は確定申告が必要!
- 医療費控除、寄附金控除、雑損控除は年末調整では計算されないので申告するとお得!
- 2024年の確定申告期限は3月15日。還付(税金が戻ってくる)申告は5年間申告できる!
会社員などの給与所得者は、原則として確定申告をする必要はありません。
通常、会社員の場合には、毎月給料から所得税が源泉徴収されていて、会社が年末に年末調整を行うことで、所得税の納税手続きが完了しているからです。
しかし会社員でも、副業などの収入が20万円を超える人や2カ所以上から給与をもらっている人、給与が2,000万円以上の人などは、確定申告を行う必要があります。
また、医療費控除、寄附金控除、雑損控除は年末調整では計算されないので、これらの控除に該当する人は、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。その他、年の途中で会社を退職して再就職していない人や、配当や原稿料などの収入があった人も、税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告の豆知識
会社員は、年末調整で所得税の清算が済んでいるので基本的に確定申告は不要ですが、確定申告は必要なくても確定申告をすれば税金が戻ってくるケースがあります。
たとえば、多額の医療費がかかったり、住宅ローンを借りてマイホームを購入した場合、寄付をした場合などです。
そのほか年末調整をする前に退職したり、年末調整で申告できなかった控除があったりする場合、退職金を受け取ったときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合にも確定申告をすれば税金が戻ってくるケースがあります。
この他にも確定申告をすれば税金が戻ってくるケースは多々ありますが、知らずに確定申告をしなかったことで、税金を納め過ぎてしまっている人もいます。
確定申告は毎年3月15日までに行う必要がありますが、還付申告は5年前までさかのぼって申告することができます。「ふるさと納税したのに、寄附金控除の申告を忘れてしまった」という場合にも、諦めずに申告を行いましょう。
そもそも確定申告とは
確定申告とは、個人や法人が所得税を納めるために税務署に申告する手続きです。
ただし、確定申告はすべての人が行わなければならない手続きというわけではありません。
たとえば会社員などの給与所得者は、勤務する会社が代わりに申告・納税を行ってくれるので、原則として自分自身で確定申告を行う必要はありません。
※会社は、社員の給料や賞与から税金(所得税と住民税)と社会保険料を徴収し、税務署や市区町村、年金事務所に納めています。
さらに年末には年末調整を行って、それまで納めてきた所得税が多すぎたり少なすぎたりしないよう、徴収した所得税との過不足を調整しています。
(1)2024年の確定申告は3月15日まで
2023年(令和5年)分の確定申告は、2024年(令和6年)2月16日(金)から、2023年(令和6年)3月15日(金)までに行う必要があります。
この期限までに確定申告を行わないと、無申告加算税がかかったり延滞税がかかったりしますので、忘れずに確定申告を行いましょう。
なお、所得税もこの3月15日までに納める必要がありますが、税金を一度に支払えない時は「延納」という制度を利用することもできます。3月15日までに納税額の2分の1以上を納めれば、残りは5月31日までに納めればよいことになります(ただし利子税がかかることがあります)。
なお、税金が戻ってくる還付申告は、5年前までの分なら、さかのぼって申告することができます。「計算してみたら、家族の医療費が10万円を超えていた」といったケースはよくあるので、領収書や交通費のメモはきちんと残しておきましょう。
(2)確定申告が必要な人・トクする人・不要な人
会社員は、確定申告は基本的に不要ですが、年収が2000万円を超えている人、副業の所得額が20万円を超えたりしている人などは確定申告が必要です。
また、確定申告の義務はなくても申告をすることで、税金が戻ってトクすることもあります。
以下に、確定申告が必要な人・確定申告をするとトクする人、確定申告が費用な人の主なケースをまとめました。それぞれのケースについては、後ほど詳しくご紹介しますが、まずは「自分の場合には、確定申告が必要なのか、した方がいいのか」について判断する際の参考にしてください。
| 確定申告が必要な例 |
| ・給与による収入金額(年収)が、2,000万円を超えている ・副業による所得(収入-必要経費)が20万円を超えている ・給与を2カ所以上からもらっていて、年末調整されなかった方の給与の収入金額と各種の所得金額が20万円を超えている ・災害減免法が適用され、源泉徴収税の猶予または還付を受けている ・外国の企業や在日の外国公館に勤務しているなど、源泉徴収されない給与の支払いを受けている ・同族会社の役員やその親族などが、その同族会社から給与の他に貸付金の利子、店舗や工場などの賃貸料、機械や工具の使用料などをもらっている |
| 確定申告でトクする可能性がある例 |
| ・自分と配偶者、同一生計の親族のために支払った医療費がおよそ10万円を超えている ・自分と配偶者、同一生計の親族のために支払った特定のOTC医薬品の購入費が1万2,000円を超えている ・国や地方公共団体、認定NPO法人などに寄附をした ・政党または政治資金団体に寄付をした ・ふるさと納税をした ・住宅ローンを組んでマイホームを新築などした ・住宅ローンを組んでマイホームを増改築した ・マイホームの住宅耐震改修を行った ・所有している居住用家屋の一般省エネ改修工事を行った ・所有している居住用家屋のバリアフリー改修工事を行った ・所有している居住用家屋の多世帯同居改修工事を行った |
| 確定申告が不要な例 |
| ・給与所得者で年末調整が済んでおり、他に適用を受けたい控除がない ・給与所得者で、副業による所得が20万円以下 ・1年間の所得が48万円以下 ・公的年金などの収入金額が400万円以下、かつ年金以外の所得が20万円以下 ・障がい年金や遺族年金を受け取った ・失業保険など、雇用保険の給付金を受け取った ・源泉徴収される特定口座で上場株式などの取引をしている ・宝くじの当選金を受け取った ・出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金を受け取った ・手術手当金や入金手当金など、保険会社の給付金を受け取った |
会社員でも確定申告が必要な人
会社員は、原則として自分自身で確定申告を行う必要はありません。
しかし、以下のようなケースでは、確定申告を行なう必要があり、もし申告をしないでいると、無申告加算税というペナルティが科されてしまいます。
|
(1)副業による所得が20万円超 (2)給与の年間収入が2,000万円超 (3)2カ所以上から給与を受けている (4)満期保険、解約返戻金が一定額を超えた (5)その他、災害減免法が適用され、源泉徴収税の猶予または還付を受けている人、外国の企業や在日の外国公館に勤務しているなど、源泉徴収されない給与の支払いを受けている人など |
(1)副業による所得が20万円超
執筆やアフィリエイト、FXなどの副業による所得が20万円以上ある人は、会社員でも「雑所得」として確定申告をする必要があります。所得税は、1年間の合計所得に対して課税されるからです。
この所得は収入から経費を差し引いた額なので、まずは経費がいくらかかったのか、所得金額がいくらになるかを確認することが必要です。
たとえば商品を仕入れて売った場合には、仕入れの金額や送料などが経費になりますし、執筆業の場合には、調査のために購入した書籍などが経費になります。
これらのすべての経費を差し引いた所得が20万円を超えたときには、確定申告が必要となります。したがって、経費はもらさず計上することが節税につながります。
なお、講演や執筆などの仕事の場合には、所得税が報酬からすでに源泉徴収されていることが多いので、その場合には確定申告することで払い過ぎた所得税が還付されることがあります。
YouTuberやUber Eatsの配達などについても、その所得が年間20万円以下であれば、確定申告は原則として不要、20万円超なら雑所得として確定申告が必要です。
副業ではなく専業で行っている場合には、年間所得(収入から必要経費を引いた額)が48万円以上であれば、個人事業主扱いとなり、事業所得として確定申告が必要です。
なお、副業について確定申告をすると「会社に知られてしまうのではないか」と心配する方もいらっしゃると思います。
この場合、確かに確定申告をすると原則として副業の所得に対する住民税額が会社に通知されますので、副業のことが会社に知られることになります。
サラリーマンの場合には、住民税は特別徴収であり、給与から天引きされるのですが、確定申告をすると、原則として副業の所得も合わせた住民税額が会社に通知されるからです。
この時、確定申告する際に申告書第二票「住民税に関する事項」の「自分で納付」に○をつけておくと、給与・雑所得以外の所得にかかる住民税は会社に通知されることはありません。だからといって、会社の担当者からすれば、会社に通知が来ないことに疑問を持たれても不思議ではありません。後日市区町村から住民税の納税通知書が届くので、案内に従って、自分で納付しましょう。
(2)給与の年間収入が2,000万円超
1年間の給与収入が2,000万を超える人は、年末調整が行われないので自分で確定申告をしなければなりません。
つまり、年末調整で行う社会保険料控除や配偶者控除などの計算がされていないので、自分で確定申告を行って所得控除を行わなければならないのです。
この際、所得が給与所得だけのケースであれば、税金が還付されるのがほとんどです。
なお、年末調整を受けた会社員の場合には、副業による所得が20万円を超えなければ確定申告の必要はありませんが、確定申告や還付申告をする場合には、主な給与以外の所得がたとえ20万円以下であっても、その所得も含めて申告しなければならないことになっています。
つまり、給与の年間収入が2,000万円超の人は、20万円以下の他の所得も確定申告しなければなりません。
(3)2カ所以上から給与を受けている
2カ所以上から給与をもらっている場合には、各会社で源泉徴収や年末調整をしても、正しい納税額を計算することができません。
そこで、給与を得ているすべての会社から源泉徴収票をもらって給与を合算し、給与所得を計算し直して自分で確定申告をする必要があります。
ただし、メインで働いている会社の給与以外の所得と退職所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
(4)満期保険、解約返戻金が一定額を超えた
生命保険や損害保険の満期保険金や、保険を中途解約して解約返戻金を受け取ったときには、「一時所得」として課税対象となります。
一時所得は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額と、特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算します。
| 総収入金額ーその収入を得るための支出額ー特別控除額(最高50万円) |
満期保険、解約返戻金は、収入のイメージがないので確定申告を忘れてしまいがちですが、税務署に指摘されると加算税、延滞税などの追徴課税が課される場合がありますので注意が必要です。
なお、生命保険は全額を一度に受け取ったときには一時所得となり、年金形式で受け取る時には雑所得となるため、計算方法が変わります。不明点等は、早めに税理士に相談しましょう。
(5)その他
その他、以下のケースに該当する場合にも、確定申告が必要となります。
|
・災害減免法が適用され、源泉徴収税の猶予または還付を受けている ・外国の起業や在日の外国公館に勤務しているなど、源泉徴収されない給与の支払いを受けている ・同族会社の役員やその親族などが、その同族会社から給与の他に貸付金の利子、店舗や工場などの賃貸料、機械や工具の使用料などをもらっている |
会社員で確定申告をすると得する人
確定申告を行う必要がない人でも、申告することで税金の還付(税金が戻ってくること)を受けたり、税金を支払わなくて済んだりする場合もあります。
たとえば所得控除とは、所得金額から控除できる金額のことですが、医療費控除、寄附金控除、雑損控除の3つは、年末調整で計算されません。ですから、これらの控除に該当する人は確定申告をすると税金が戻ってくることになります。
|
(1)ローンを組んで自宅を購入・増改築した (2)バリアフリー、省エネ等の改修工事をした (3)自宅売却で譲渡損が出た (4)株式配当金をもらった(改正) (5)ふるさと納税などの寄附を行った (6)指定の市販薬を1万2,000円以上購入した (7)年間の医療費が10万円を超えた (8)株式やFXなどの投資で損失が出た (9)年末調整で生命保険などの控除申告をしなかった (10)台風・地震・火災・盗難の被害を受けた (11)年の途中で退職して再就職していない (12)「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない (13)不動産を売却して利益が出た (14)特定支出控除の特例を受けたい |
確定申告をするとトクする人は意外と多いのですが、それを知らなかったために確定申告をしないで、恩恵を受けられないのは大変もったいないことです。
まずは、自分が確定申告すべきか否かについて確認し、該当する場合には、忘れずに申告をするようにしましょう。
(1)ローンを組んで自宅を購入・増改築した
住宅ローンを組んでマイホームを購入すると、住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)で税負担を軽減することができます。
適用を受けるためには、住宅の新築・取得から6カ月以内に居住している、ローンの返済期間が10年以上、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下、登記簿上の床面積が50㎡以上などの要件があります。
会社員の場合は、最初の年に確定申告をすれば、翌年からは勤務先の会社の年末調整で引き続き控除を受けることができます。一方、個人事業主は2年目以降も自分で申告します。
住宅ローン控除は、2021年までの予定でしたが、改正により2025年まで延長されました。ただし、2025年末で控除が受けられなくなるわけではなく、新築・取得した住宅に2025年末までに入居すれば、最長13年間にわたり控除が適用されます。
(2)バリアフリー、省エネ等の改修工事をした
住宅ローン控除は、住宅のリフォームも対象となります。
リフォームする際のローンの返済期間が10年以上、改修工事にかかった費用が100万円以上などの要件を満たしていれば、年末ローン残高の0.7%を10年間にわたり控除することができます。
なお、ローン利用の有無を問わず適用できる控除として「住宅特定改修特別税額控除」「住宅耐震改修特別控除」があります。
こちらは、控除を受けられるのは申告した年だけです。
(3)マイホーム売却で譲渡損が出た
マイホームを売却した損失は、一定の要件を満たせば給与所得など他の所得と損益通算することができ、通算しきれなかった赤字を繰り越すことができます。通算した結果、給与などから1年間に源泉徴収された税金が戻ってくることがあります。
ただしマイホームの売却損には、別荘などを売却したときの赤字は含まれませんので注意が必要です。
損益通算できるのは、以下の2つのケースで、いずれの場合も売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えていることが前提です。
|
①マイホームの買換えをして、新しく購入した家に住宅ローンを組んだ(居住用財産の買換え時の場合の譲渡損失) ②マイホーム売却代金以上の住宅ローンが残っている(特定居住用財産の譲渡損失) |
(4)株式配当金をもらった
株の配当や投資信託の収益の分配(公社債投資信託と公募公社債等運用投資信託をのぞく)がある時には、配当所得を申告します。
上場株式等の配当については申告しなくてもよいことになっていますが、申告した方が有利なケースもあります。
|
①課税所得が695万円以下 課税所得が695万円以下で、所得税率が20%以下の人は申告した方が有利です。 ②課税所得が900万円未満 ③株式売買で損失が出た |
(5)株式やFXなどの投資で損失が出た
上場株式の譲渡損は、他の所得とは通算できませんが、他の上場株式の売却益や申告分離課税を選択した配当所得等とは通算が可能です。
損失を出した年に確定申告をすれば、繰越控除をすることもできます。
たとえば、2つの証券会社に口座を開設していて、一方の源泉徴収口座で利益が出て税金が差し引かれていて、もう一方の一般口座で損失が出ていれば、上場株式等同士であれば、確定申告をして還付を受けられます。
(6)ふるさと納税などの寄附を行った
ふるさと納税をした人や、法律で定められた特定の団体や組織に寄附をした人は、寄附金控除を受けることで、税金が戻ってくる可能性があります。
個人住民税の還付金額は限度があるので、所得金額や寄附金額によっては、寄附金全額が戻るわけではありませんので、限度額を超えないように寄附するようにしましょう。
確定申告不要な給与所得者等については、ふるさと納税先が5団体以下であれば、納税先団体に申請することで確定申告不要となるワンストップ特例制度もあります。
なお、専業主婦は所得税や住民税を納めていないので、「納税者」ではありません。いくらふるさと納税をしてもその他の寄附を行ったとしても、税制上のメリットはありませんので注意が必要です。
(7)指定の市販薬を1万2,000円以上購入した
健康の保持増進および疾病の予防として、一定の取り組みを行っている人が、自分や自分と同一生計の親族にかかる「特定一般用医薬品等購入費」を支払った場合で、その年中に支払った対価の合計額が1万2,000円を超える人は、その超える部分の金額が、その年の総所得金額から控除されます(8万8,000円を超える場合には8万8,000円)。
なお、保険金や損害賠償金などで補てんされる部分はのぞきます。
(8)年間の医療費が10万円を超えた
病気やケガなどで医療費(交通費、薬代含む)に該当する出費が、年間で10万円を超えるか、所得の5%以上の医療費を支払った場合には、医療費控除を受けられる可能性があります。家族全員の医療費の合計額が対象となります。
控除額の上限は最高200万円までで、「医療費の額-保険金などで補てんされる金額-10万円」もしくは「合計所得金額の5%」のいずれか低い方が控除されます。
|
「1年間に支払った医療費」-「保険金ほか各種補てん金」-「(給与所得金額200万円以上の人)10万円」 もしくは 「(給与所得金額200万円未満の人)総所得金額×5%」=「医療費控除 最高200万円」 |
年末調整では医療費控除はされないので、確定申告をしなければ税金はもどってきません。もれなく確定申告をするようにしましょう。なお、医療費控除は、自分の医療費だけでなく家族の医療費をすべて合計して申告することができます。
※インフルエンザなどの予防接種費用や美容上の費用、人間ドックの費用などは医療費控除の対象とはなりません。
例外として、人間ドックで重大な病気が発見されて、引き続き検査・入院するような場合には対象となります。
(9)台風・地震・火災・盗難の被害を受けた
台風や火災などで住宅や家財に損害を受けた場合には、税金を軽減する制度があります。住宅や家財に損害を受けた場合には、税金を軽減する制度があります。
災害については、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下であれば、災害減免法による所得税の軽減免除を受けることが可能ですが、雑損控除(所得控除)と災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)のどちらか有利な方を選択できますが、両方適用することはできません。
(10)年末調整で生命保険などの控除申告をしなかった
生命保険料控除や地震保険料控除は、年末調整の際に申告するのを忘れるケースが多いのですが、その場合には確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。
本人が本人や家族を受取人とする生命保険の生命保険料または共済掛金を支払った場合には、所得の金額から一定の額を控除することができます。
また、本人や家族が常時住んでいる家屋や家財等の地震保険料を支払った場合にも、所得の金額から一定の額を控除することができます。
生命保険料控除額や地震保険料控除額は、契約締結年や支払った保険料について異なりますが、以下の記事でご紹介しておりますので、あわせてご覧ください。
▶ 生命保険料控除・地震保険料控除|確定申告書の書き方・控除額の計算方法
(11)年の途中で退職して再就職していない
年の途中で退職して再就職していない人は、毎月の給料から所得税が源泉徴収していたのに、年末調整を受けていないことになります。
源泉徴収税額は、月々の給料から控除されますが、その給料は「年間を通して受け取った」と仮定した場合の所得税をベースに、計算しています。
このような場合には、多くのケースで税金を払い過ぎているので、年の途中で退職して再就職していない人は、確定申告をすると所得税が戻るケースがほとんどです。
なお確定申告をすれば、改めて市区町村に住民税の申告をする必要はありません。
また、退職後再就職していれば、再就職先で前職分も一緒に年末調整をしてもらえるので原則として確定申告をする必要はありません。
ただし年金をもらった場合には、年金の分を給与所得と一緒に確定申告をすることになります。
(12)「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
退職所得については、通常は「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、支払いを受けた時にすでに税金が差し引かれているので、確定申告は不要です。
しかし、退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないで会社を退職した場合には、支払われた退職金から一律20.42%(復興特別所得税含む)が源泉徴収されているので、税金を払い過ぎている可能性があります。
退職所得の所得税は非常に優遇されていて、以下の計算式で計算します。
※ |
退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、かならず確定申告をするようにしましょう。
(13)マイホームの売却益は優遇されている
不動産(土地、建物)を売却して利益が出た人は、譲渡所得として税金がかかるので、確定申告をする必要があります。
税率は、不動産の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点で、その不動産を所有していた期間によって異なります。
しかし、譲渡した不動産が自分の住んでいるマイホームであった場合には、譲渡益が3,000万円までは税金がかかりません。さらに10年以上所有していたマイホームを譲渡した場合には、3,000万円の控除後の所得金額に対して、通常より低い10%の税率が適用されます(そのうち6,000万円を超える部分は15%)。
さらに、マイホームを売却して損失が出た場合には、確定申告をすると給与などほかの所得から控除することができます。
※買替えで損が出た場合の特例は「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。
また、住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が出た時の特例は「特定のマイホーム所の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。
これらの特例を使うと、損失額をその年の給与所得等から控除できます。そして、その年の所得から控除しきれなかった損失額は、最大3年間繰り越して控除することができます。
ただし、これらの特例を使うための要件は厳しく定められているので、適用されるか否かの判断は困難です。特別控除を適用したい場合には、税理士に相談するようにしましょう。
(14)特定支出控除の特例を受けたい
特定支出とは、以下の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、給与所得控除額を差し引いた残りの額から、さらにその超える部分の金額を控除することができる特例です。
|
①通勤のために通常必要と認められる支出(通勤費) ②職務遂行上直接必要な旅費等の支出 ③転勤に伴う通常必要と認められる転居費 ④職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として受ける研修費 ⑤職務に直接必要な資格を取得するための支出 ⑥単身赴任などで、その人の勤務地または居所と自宅の間の旅行等に通常必要な支出 ⑦勤務上必要な経費(上限65万円までの図書費、衣服費、交際費等) |
この特定支出控除の特例の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。令和5年分からは、特定支出のうち資格取得費と研修費(教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練に関するもの)に必要な証明書は、給与等の支払い者によって証明されたもののほか、キャリアコンサルタントによって証明されたものも認められることになりました。
まとめ
以上、会社員でも確定申告する必要がある人、しないと損する人についてご紹介しました。確定申告をすればトクするケースはここでご紹介したケース以外にもあります。知らずに確定申告をしないでいると、税金を納め過ぎてしまいますので、不安な場合は税理士に相談するなどして確定申告を行なうことをおすすめします。
会社員の確定申告について相談する
freee税理士検索では数多くの事務所の中から、会社員の確定申告について相談できる税理士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
\ 固変分解について相談できる税理士を検索 /
この記事の監修者:遠藤光寛税理士事務所

監修者
遠藤 光寛えんどう みつひろ
遠藤光寛税理士事務所 代表
法人・個人の皆様の「お金の問題」に誠実に対応し解決します!
サラリーマンは、給与から税金を源泉徴収され、会社の年末調整で税金を清算します。しかし、年末調整を受けられない場合や年末調整で清算されない一部控除もあります。確定申告によってこれらの控除を申請すれば、税金が還付されることがあります。自分に当てはまる控除がないかもれなくチェックし、適切に確定申告を行いましょう。不明点や疑問点等があれば、当事務所がサポートします。お気軽にお問合せください。
- ・分離課税|総合課税との違いは?「源泉分離課税」とは?
- ・必要経費の種類と勘定科目一覧-個人の確定申告
- ・扶養控除とは|控除を受けられる要件とトクする利用法
- ・請書(うけしょ)に印紙は必要?請書に貼る印紙の金額は?
- ・競馬にかかる税金はいくらから?ハズレ馬券は経費になる?
- ・専従者給与とは|家族に支払った給与を経費にできる節税方法
- ・小規模企業共済とは|5つのメリットと3つのデメリット
- ・所得金額調整控除とは|計算方法は?適用要件は?
- ・配当控除とは|計算方法は?有利不利の判定は?
- ・複式簿記とは|単式簿記との違い・決算書との関係【初心者向け】
- ・貸方・借方とは|意味・仕訳の方法&決算書との関係
- ・副業の確定申告|20万円超の所得は申告が必要|方法、必要書類を解説
- ・個人事業主の節税対策|経費を増やして税金を減らす11の方法
- ・簿記とは|これから学ぶ人のために図入りで分かりやすく
- ・事業主貸と事業主借の違いと仕訳例|個人事業主の勘定科目
- ・そもそも「控除」って何?節税になる所得控除、税額控除とは
- ・キャッシュ・フローとは|3分で分かるキャッシュ・フロー計算書の基本
- ・特定口座とは?源泉あり、源泉なしのメリット・デメリット
- ・基礎控除とは|控除額・計算方法・還付の方法
- ・確定申告してから還付金を受け取るまでのスケジュール
- ・サラリーマンの確定申告|年末調整をしていても確定申告が必要な場合とは
- ・会社員でも確定申告が必要な人・申告しないと損する人【2022年度版】
- ・一時所得とは|確定申告が必要な場合とは?
- ・確定申告書Aとは|確定申告書Bとの違いと記入方法(図入り)
- ・減価償却とは|「そもそも減価償却って何?」から図入りで分かりやすく
- ・退職した人の確定申告|退職後税金が確定申告で戻ってくる場合とは
- ・課税証明書とは?必要になる場面と入手方法を解説
- ・EPS(1株当たり利益)とは|計算方法とPERとの関係
- ・元入金(もといれきん)|意味は?計算方法は?(仕訳例付き)
- ・貸借対照表とは|構造・ルール・見方・ポイントまとめ
- ・一括償却資産とは|減価償却資産&少額資産償却制度との違い